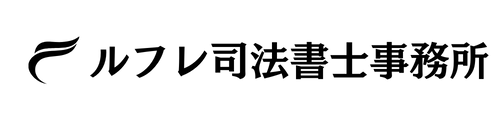不動産を生前贈与するメリット・デメリットは?税金や手続きを分かりやすく解説

不動産の生前贈与について考えている方へ。このページでは、不動産を生前贈与する際の基本的な知識や、手続きの流れ、税金に関する情報を詳しく解説しています。「不動産を贈与したいけれど、どのように進めればよいのかわからない」「贈与と相続の違いや、それぞれのメリットとデメリットについて知りたい」という疑問をお持ちの方に役立つ内容を網羅しています。また、具体的な注意点も盛り込んでいるため、実際の手続きで役立つこと間違いなしです。この記事を読むことで、生前贈与のメリット・デメリットを正確に把握し、納得のいく計画を立てることができます。
不動産を生前贈与とは何か
不動産の生前贈与とは、生きている間に自分の所有する土地や建物等の不動産を特定の相手に譲り渡すことを指します。この手続きは、将来の相続税対策や、自分が望む形で財産を承継させたいといった理由で行われることが多いです。
手続きには贈与税や各種手数料、税金の申告が伴うため、事前に注意点を理解しておくことが重要です。
不動産を生前贈与するメリット
不動産を生前贈与するメリットはたくさんありますが、いくつか下記で説明します。下記以外にもご自身が認知症になる前に、お子さんへ不動産の名義変更をする認知症対策として利用される方や、ご自身の意思で特定の方に確実に不動産を譲渡したいと考えている方が、利用されるケースも多いです。
相続税対策になる
不動産を生前贈与する最大のメリットは、相続税対策として有効であることです。生前贈与を行うことで、贈与された不動産の評価額を相続財産から事前に減らすことができ、結果的に将来の相続税の課税対象額を抑えることができます。さらに、贈与に適用できる控除や特例を活用することにより、相続税をより一層軽減することも可能です。
たとえば、親が所有している土地や建物を生前に贈与することで、その不動産の評価額分が相続税評価額から減額されます。また、相続開始時に不動産の価値が上がっていた場合でも、贈与時の評価額で課税計算されるため、価値上昇による課税リスクを減らすことができます。
財産を有効活用できる
生前贈与をすることで、自分の財産を有効に活用する道が広がります。例えば、子どもや孫に不動産を贈与することで、早い段階で財産を譲り渡し、資産運用や自己利用を促進することが可能です。
具体的な例として、親名義で所有していた収益不動産を子ども名義に変更する生前贈与があります。この場合、不動産の名義変更した後は、収益が子どもに入ることになり、その収益を子どもが将来の生活費や教育費に充当することができます。さらに、子どもの資産形成を助けるとともに、家族全体の資産計画を円滑に進めることが可能です。
贈与税の軽減措置を活用できる
不動産を生前贈与する際には、贈与税の軽減措置や特例が利用できる点も大きなメリットです。代表的な特例として、「相続時精算課税制度」や「暦年贈与の非課税枠」が挙げられます。これらを活用することで、大きな税負担を避けながら円滑な贈与が可能になります。
相続時精算課税制度では、親や祖父母が子どもや孫に対して贈与する場合に2,500万円までの非課税枠が適用されます。また、暦年贈与を活用すれば、年間110万円までの非課税枠内で不動産や財産を細分化して贈与することが可能です。
これらのメリットを最大限に享受するためにも、贈与の際には通常の税制に加えて軽減措置や特例条件を十分に確認し、最善の方法を取ることが重要です。そのため、専門家や税理士への相談を早期に行うことをおすすめします。
不動産を生前贈与するデメリット
相続で取得するより、税金が高くなるケースある
不動産を生前贈与するとき、贈与税が発生する可能性があります。贈与税の軽減措置として「相続時精算課税制度」や「暦年贈与」などがありますが、どの制度を利用する場合でも、控除額を超える贈与に対して贈与税が課されます。また、生前贈与の場合、相続により取得した場合にはかからない不動産取得税がかかり、登録免許税も相続に比べて税率が5倍と高いです。
上記の理由により、最終的に支払う税金が多くなってしまうことも考えられるため、具体的なシミュレーションをすることが大切です。
手続きが煩雑な場合がある
不動産を生前贈与するにはさまざまな手続きが必要となります。贈与には贈与契約の締結や不動産の名義変更、贈与税の申告が含まれ、これら一連の手続きには煩雑な書類作成と多くの確認作業が伴います。
例えば、不動産の登記を変更する際には管轄の法務局での登記申請が必要ですが、この際に贈与契約書、登記申請書など多くの書類が求められます。不備があると再提出が必要になり、作業に余分な時間がかかります。
また、税務署への贈与税の申告も求められますが、申告書や添付書類の作成を含むこの作業も専門知識を必要とするため、スムーズに進めるには専門家への依頼を検討するのも良いでしょう。
贈与後のトラブルに発展する可能性がある
不動産の生前贈与を行うことで、贈与を受けた人や他の家族との間でトラブルが生じる可能性があります。具体的には、以下のような問題が起こることがあります。
- 他の相続人が「不公平だ」と感じ、関係悪化や相続争いを引き起こす
- 贈与された不動産の活用に関して贈与者と受贈者の間で意見が食い違う
- 受贈者が固定資産税や維持費などの費用負担に困難を感じる
これらのトラブルを回避するためには、事前にご家族で十分な話し合いを行い、同意を得ておくことが重要です。
その他の考慮点
さらに、不動産の維持管理費や固定資産税など、所有者にかかるコストも考慮しておくべきです。贈与後に思いがけない費用が発生することで、受贈者が負担に感じることがあります。
これらのリスクを軽減するためには、生前贈与を行う前に、税理士や司法書士などの専門家に相談し、具体的なシミュレーションを行うことをおすすめします。専門家の助言を得ることで、無駄な費用やトラブルを未然に防げる可能性が高まるでしょう。
不動産の生前贈与にかかる税金
贈与税
不動産を生前贈与した場合、最も大きな負担となるのが贈与税です。贈与税は、贈与によって受け取った資産の価値に応じて課税される重要な税金です。ただし、適用できる控除や特例を活用すれば、贈与税を削減することが可能です。
贈与税の計算方法
贈与税は、年間110万円の基礎控除を差し引いた残額に対して税率を適用し計算されます。土地や建物を含む贈与財産の合計金額から基礎控除額を控除し、その金額が課税対象となります。課税対象額には、以下の累進税率が適用されます。
| 課税対象額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | なし |
| 200万円超から300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超から400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超から600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 600万円超から1000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1000万円超から1500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 1500万円超から3000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3000万円超 | 55% | 400万円 |
贈与税の軽減措置
贈与税の軽減措置には、以下のような特例があります。
暦年贈与
暦年贈与は、1年間の贈与額が基礎控除額である110万円以内であれば贈与税が課せられない制度です。この制度を利用して、長い期間をかけて少しずつ財産を贈与することで、相続税を減らすことが可能です。
たとえば、毎年110万円までの不動産の持分や現金を相手に贈与することで、贈与税の負担なく財産を移転できます。ただし、贈与契約書を毎回作成し、正しい手続きを行うことが求められます。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、親や祖父母から子や孫に対する贈与に適用される制度で、最大2,500万円まで贈与税が課されない仕組みです。ただし、この制度を利用した贈与分は、贈与者が亡くなった際の相続財産として計算されます。
たとえば、不動産を生前贈与した場合でも、贈与時の評価額が相続税の課税対象となるため、相続全体で税金が発生する可能性があります。そのため、相続時精算課税制度を利用することでメリットがあるかは事前にシミュレーションが必要です。
配偶者控除
婚姻期間が20年以上の配偶者に住宅を贈与する場合、2,000万円まで非課税となります。
| 項目 | 暦年贈与 | 相続時精算課税制度 | 配偶者控除 |
|---|---|---|---|
| 控除額 | 年間110万円まで | 累計2,500万円まで | 2,000万円まで |
| 贈与後の課税 | 控除額超過分に贈与税が課せられる | 控除額超過分に一律20%の贈与税が課せられる | 暦年贈与110万円を足した2,110万円を超えた分にの贈与税が課せられる |
| 相続時の考慮 | 相続には加算されない | 相続財産として計算 | 相続には加算されない |
| 利用条件 | 特になし | 贈与者が60歳以上、受贈者が18歳以上の子または孫 | 婚姻期間が20年以上の配偶者に住宅を贈与する場合 |
登録免許税
不動産を生前贈与する際、受贈者(贈与を受けた人)は不動産登記の名義変更を行う必要があります。この際に課される税金が登録免許税です。課税額は、不動産の固定資産評価額の2%となります。
例えば、不動産の評価額が1,000万円の場合、登録免許税は20万円となります。この税率は、相続登記の際に課される登録免許税(評価額の0.4%)と比べて非常に高い点に注意してください。
不動産取得税
不動産を取得した際にかかる税金として、不動産取得税があります。この税金は、不動産を贈与された場合にも適用され、受贈者に課税されます。税率は、不動産の種類によって異なります。 総務省:不動産取得税
| 不動産の種類 | 税率 |
|---|---|
| 住宅用の建物および宅地 | 3% |
| 住宅以外の建物 | 4% |
ただし、土地(宅地)については、評価額を1/2に軽減する特例措置が適用される場合があります。また、相続によって取得した不動産には不動産取得税が課されないなどの例外もあります。
このように、不動産の生前贈与ではさまざまな税金が課されます。そのため、事前に税額のシミュレーションを行い、必要に応じて税理士や専門家に相談して対策を講じることが重要です。
不動産を生前贈与の手続き
贈与契約の締結
不動産を生前贈与するためには、まず贈与契約を締結する必要があります。これは贈与者(不動産を譲渡する人)と受贈者(不動産を受け取る人)の双方で行う合意の形です。贈与者と受贈者は、贈与契約書を作成し、どの不動産をどのような条件で贈与するのかを記載し、署名捺印します。
契約の内容には、不動産の具体的な詳細(住所や面積など)、贈与の条件、費用の負担区分(税金や登記費用の分担など)が明記されます。これにより、後々のトラブルを防ぐ効果があります。
不動産の登記手続き
不動産の所有権を移転するには、不動産の所在地を管轄する法務局での登記手続きが必要です。登記手続きの流れは、以下のようになります。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 必要書類の収集 | 印鑑証明書、住民票、固定資産評価証明書など |
| 登記申請書の作成 | 不動産の所在地を管轄する法務局に提出する登記申請書を作ります |
| 法務局への申請 | 完成した書類を提出し、登録免許税を納付します |
| 登記の完了通知 | 登記完了証と登記識別情報(不動産の権利証)を受領します |
登録免許税が固定資産評価額の2%として計算されるため、事前に評価額を確認するのがよいでしょう。また、登記に必要な法律知識や手続きが難しい場合、司法書士に依頼することで円滑に進む場合もあります。
登記手続きの必要書類
不動産の生前贈与に必要な書類は以下の通りです。事前にすべて揃えておくことで、手続きをスムーズに進められます。
| 必要な書類 | 説明 |
|---|---|
| 贈与契約書 | 贈与者と受贈者の間で締結された契約内容を記載した書類 |
| 登記識別情報(または登記済権利証) | 不動産の権利を証明するための書類 |
| 納税通知書および課税明細書又は固定資産評価証明書のコピー | 不動産の評価額を確認するため最新年度分が必要になります。 |
| 贈与者の印鑑証明書 | 発行から3か月以内 |
| 贈与を受ける人の住民票 | 受贈者の住所地を証明するための書類 |
| 登記申請書 | 不動産の名義変更を行うために法務局へ提出する書類 |
| 委任状 | 司法書士に手続きを依頼する場合 |
贈与税の申告
贈与税の課税対象となる場合、受贈者(贈与を受けた人)は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの期間に税務署で贈与税申告を行います。
相続時精算課税制度や配偶者控除などの特例を利用する場合には、上記の期限までに申告が必要になります。
「国税庁:相続時精算課税選択届出書に添付する書類」
「国税庁:夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」
これらの手続きをスムーズに進めるためには、贈与契約の段階から専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
不動産を生前贈与する際の注意点
不動産を生前贈与する際には、さまざまなメリットがありますが、それと同時にトラブルや税負担を適切に回避するための注意点もあります。計画的かつ慎重に手続きを進めることが重要です。ここでは、主に以下の3つの観点から注意点を詳しく解説していきます。
登録免許税や不動産取得税が高くなる可能性がある
不動産を生前贈与する際には、相続登記よりも高い税負担が発生する可能性があります。たとえば、登録免許税の税率が「相続の場合は0.4%」である一方、生前贈与では「2%」となります。また、不動産取得税も課税される場合があります。
以下は税率の違いを比較した表です。
| 対象土地 | 登録免許税 | 不動産取得税 |
|---|---|---|
| 相続 | 0.4% | かからない |
| 生前贈与 | 2% | 固定資産評価額の3%(土地・住宅) |
これらの点を考慮すると、不動産の評価額が高額な場合には、節税対策として相続と生前贈与のどちらが適しているのかをよく検討する必要があります。
分割贈与を計画的に進める
不動産を分割して少しずつ贈与する方法は、暦年贈与制度を活用できるため節税効果が高い一方で、計画的に進めなければトラブルや未完了部分が発生する危険性もあります。
分割贈与を進める際の注意点は以下の通りです。
- 毎回の贈与契約書を作成し、贈与の事実を明確にする
- 贈与が完了する前に贈与者が亡くなった場合のリスクを考慮する
例えば、不動産の持分を年単位で分割贈与する場合、毎年、基礎控除の110万円を超えない範囲で、持分を贈与することになるため、不動産の全てを受贈者が取得するのに長い年月がかかります。分割贈与の途中で贈与者が亡くなってしまうことがないように、贈与者の年齢も考えて計画的に行う必要があります。
住宅ローンが残っている不動産の贈与
住宅ローンが残っている不動産を生前贈与する場合、まず考慮すべきはローンの残債務と金融機関の同意です。一般的に不動産を贈与する際には、その所有権が移転しますが、住宅ローンの債務は贈与の対象に含まれません。そのため、現状のローン契約に基づいて所有者が変更される場合には、金融機関の承諾が必要となることがあります。また、ローンの残債務がある場合、その債務について贈与契約書に事前に明確に取り決める必要があります。
このような住宅ローンの残高を含む不動産の贈与は複雑な手続きが必要なため、金融機関や司法書士、税理士などの専門家と相談しながら進めることをお勧めします。
まとめ
不動産の生前贈与は、相続税対策や財産の有効活用といったメリットがありますが、一方で贈与税や煩雑な手続きといったデメリットも伴います。さらに、税金対策として暦年贈与や相続時精算課税制度などの選択肢があり、それらを正しく理解し活用することが重要です。また、贈与契約や登記手続き、税金の申告については正確な対応が求められるため、専門家のサポートを受けることも検討しましょう。最終的には、贈与後の関係性やトラブルを避ける配慮もしながら計画的に進めることが、円満な贈与につながります。この記事を参考に、家族の意思を十分に確認し、最適な方法を選んでみてください。
ルフレ司法書士事務所では、生前贈与をはじめ、遺言書作成、家族信託、財産管理等委任契約、死後事務委任契約など、生前対策に関する様々な業務を扱っております。司法書士が、迅速丁寧にお客様の状況に合わせた最適なサポートを提供いたします。また、ご希望に応じて他士業(弁護士さんや税理士さん)を紹介しております。
全国対応していますので、生前対策でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。