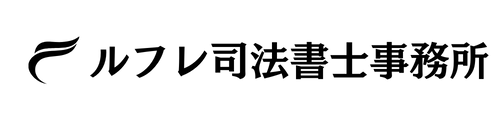任意後見制度とは?家族が知っておくべき基本情報

将来、判断能力が低下した場合に備え、自分の財産管理や生活をサポートしてくれる人をあらかじめ自分で決めておくことができる制度、それが任意後見制度です。
将来、もしものことがあったときに、あなたの意思を尊重し、適切なサポートを受けられるようにするための大切な仕組みです。この記事では、任意後見制度の概要から、後見人の役割、手続きの流れ、メリット・デメリット、費用についてまで、分かりやすく丁寧に解説します。複雑で分かりにくいと思われがちな任意後見制度ですが、この記事を読めば、制度の全体像を理解し、自分にとって必要な準備を始めることができます。元気なうちに将来に備え、安心して生活を送るために、ぜひこの記事を参考にしてください。
任意後見人制度とは
まず初めに任意後見人制度の概要と、法定後見制度との違いについてを解説します。
任意後見人制度とは
任意後見制度とは、将来、ご自身の判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ後見人となってくれる人と契約を締結し、どのような支援をしてもらいたいかを定めておく制度です。元気なうちに、信頼できる人と公正証書によって契約を結び、将来の安心を確保します。
任意後見契約は、将来の不測の事態に備えるためのものなので、契約締結後すぐに効力が発生するわけではありません。本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が「後見監督人」を選任して初めて、任意後見契約の効力が発生し、後見人が活動を開始します。後見監督人は、任意後見人が適切に任務を遂行しているかを確認する役割を担い、通常は司法書士や弁護士などの専門家が選任されます。 厚生労働省:任意後見制度とは
法定後見制度と任意後見制度
成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。どちらの制度を利用するかは、現在の判断能力によって決まります。すでに判断能力が不十分な場合は法定後見制度、まだ判断能力があるうちに将来に備えたい場合は任意後見制度を利用します。
- 任意後見制度:判断能力がある方が対象
- 法定後見制度:既に判断能力が不十分な方が対象
以下の表で、任意後見と法定後見の違いを分かりやすく比較しています。
| 項目 | 任意後見 | 法定後見 |
|---|---|---|
| 対象者 | 将来、判断能力が不十分になる可能性がある人 | すでに判断能力が不十分な人 |
| 開始時期 | 本人の判断能力が不十分になったとき (家庭裁判所が後見監督人を選任した時点) | 家庭裁判所が後見開始の審判をしたとき |
| 後見人の選任方法 | 本人が事前に決定 | 家庭裁判所が決定 |
| 取消権 | なし | あり |
任意後見制度のメリットとデメリット
任意後見制度には、メリットとデメリットがあります。それぞれのメリット・デメリットを理解しておきましょう。
メリット
- 希望に応じた内容に後見人の権限を設定できる:法律で後見人ができることが決まっている法定後見と違い、任意後見の場合は、自由に設定することができます。
- 後見人を自ら選ぶことができる:信頼できる家族、友人、専門家など、自身で後見人を選ぶことができます。
- 希望する生活を送れる:将来の生活、医療、介護、財産管理などについて、事前に希望を具体的に決めておくことができます。例えば、住み慣れた自宅で最期まで過ごしたい、特定の施設に入居したい、財産をどのように使ってほしいかなど、自身の意思を反映させることができます。
- 後見監督人による監督:後見監督人が、後見人が適切に業務を行っているか監督します。これにより、後見人による不正や不適切な行為を防ぎ、本人の利益を守ることができます。
デメリット
- 取消権がない:法定後見と違い、任意後見の場合には、後見人に本人が不利な契約を結んだ場合にその契約を取り消す「取消権」がありません。このため、任意後見制度では本人の保護がやや弱い側面があります。
- 費用がかかる:任意後見契約の公正証書作成費用、将来の任意後見監督人選任の申立費用、任意後見監督人への報酬、任意後見人への報酬(専門家を依頼する場合)など、一定の費用がかかります。費用の負担についても考慮に入れて、制度の利用を検討する必要があります。
- 手続きが必要:公正証書の作成、任意後見監督人選任の申立てなど、一定の手続きが必要です。手続きが煩雑に感じる場合もあるため、専門家に相談しながら進めることが推奨されます。
任意後見制度の手続きの流れ(ご本人の判断能力が低下する前)
任意後見制度を利用する場合の手続きの流れは下記のようになります。
1 任意後見人を決める
⇩
2 支援内容を決める
⇩
3 任意後見契約を公正証書で作成する
⇩
4 公証人の嘱託により後見登記がされる
任意後見人を決める
まずは将来自分を支援してくれる人、つまり、任意後見人になってくれる人を決めます。任意後見人は、あなたの判断能力が衰えてきた際に、財産管理などの重要な仕事を任せる人になるので、信頼できる人に依頼することが非常に大切です。家族や親族、友人など、あなたのことをよく理解し、あなたの意思を尊重してくれる人を選びましょう。また、司法書士などの専門家を選ぶことも可能です。専門家は法律や手続きに精通しており、客観的な立場から適切なサポートを提供してくれます。複数名を選任することも可能です。
支援内容を決める
任意後見人が決まったら、支援内容を決定します。判断能力が衰えてきた時に、何について、どのように支援してもらいたいかを具体的に決めておく必要があります。例えば、「介護サービスを利用しながら自宅で生活を続けたい」「自宅を売却して老人ホームに入居したい」など、あなたの希望を明確に伝え、契約内容に反映させましょう。契約内容が詳細であればあるほど、将来のあなたの意思が尊重されやすくなります。主な内容としては、生活、介護、療養、医療に関すること、財産の管理・処分・利用方法、任意後見人の報酬、任意後見人に依頼する事務の範囲などが挙げられます。後見人が財産をどのように管理するか、医療や介護についてどのような決定を任せるかなど、具体的に定めておくことが重要です。
任意後見契約を公正証書で作成する
任意後見契約は、法律で公正証書で作成することが義務付けられています。公正証書は、公証役場で作成される公文書であり、高い証明力を持つため、将来のトラブル防止に役立ちます。公証役場へは、契約内容をまとめた原案と必要書類(本人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、任意後見受任者の印鑑証明書など)を持参します。公証人は、契約内容を確認し、公正証書を作成します。公正証書作成の手数料は、契約内容によって異なりますが、目安として1万円~2万円程度です。
公証人の嘱託により後見登記がされる
任意後見契約が公正証書で作成された後、公証人の嘱託により後見登記がされます。後見登記が完了すると、任意後見人の氏名や代理権の範囲を記載した登記事項証明書を取得することができるようになります。登記事項証明書は、任意後見人が金融機関や役所で手続きを行う際に、任意後見人としての資格を証明する重要な書類です。
任意後見制度の手続きの流れ(ご本人の判断能力が低下した後)
ご本人の判断能力が低下した後の手続きの流れは下記のようになります。
【ご本人の判断能力が低下した後】
1 後見監督人選任の申立て
⇩
2 後見監督人の選任
⇩
3 任意後見人の職務開始
後見監督人選任の申立て
ご本人の判断能力が低下し、任意後見契約に基づく支援が必要になった場合、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任の申立てを行います。任意後見監督人は、任意後見人が適切に職務を遂行しているか監督する役割を担います。申立ては、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見の受任者が行うことができます。申立先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。申立てに必要な書類は、申立書、本人の事情説明書、任意後見契約公正証書のコピーなどです。費用は、申立手数料800円、登記手数料 1400円、郵便切手代(申立をする裁判所に確認)などがかかります。
後見監督人の選任
家庭裁判所は、申立ての内容を審査し、任意後見監督人を選任します。任意後見監督人は、通常、弁護士や司法書士などの専門家が選任されます。任意後見監督人は、任意後見人が契約内容に従って適切に職務を遂行しているか監督し、家庭裁判所へ報告する義務を負います。任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定し、本人の財産から支払われます。月額報酬の目安は、月額1万円~3万円程度です。
任意後見人の職務開始
任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が発生し、任意後見人は、契約内容に基づいて、あなたの財産管理や身上監護などの業務を開始します。任意後見人は、定期的に家庭裁判所へ報告する義務があり、任意後見監督人は、その報告内容を審査し、必要に応じて家庭裁判所へ意見を述べます。任意後見人の報酬は、任意後見契約で定められた金額が、本人の財産から支払われます。家族が任意後見人の場合は無償の場合もありますが、専門家の場合は月額3万円~6万円程度が相場です。
任意後見人の役割について
こちらでは、任意後見人の職務内容や選び方、そして報酬について説明します。
任意後見人とは
任意後見人とは、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、ご本人が選任した代理人です。本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が選任した後見監督人の監視のもと、任意後見契約で定めた内容に基づき、本人の財産管理や身上監護を行います。公正証書で作成された任意後見契約の内容に従って、本人の意思を尊重し、適切なサポートを提供することが重要です。
任意後見人の職務内容
任意後見人の職務内容は、大きく「財産管理」と「身上監護」の2つに分けられます。契約内容によって、どこまで権限を与えるかは自由に決定できます。
財産管理
財産管理とは、本人の預貯金、不動産などの財産を適切に管理することです。具体的には、下記のような業務が含まれます。
| 財産管理業務 | 具体例 |
|---|---|
| 不動産の管理・処分 | 自宅の維持管理、賃貸借契約、売却 |
| 預貯金の管理 | 入出金、振込、定期預金の解約 |
| 有価証券の管理 | 株式の売買、配当金の受け取り |
| 年金の管理 | 年金受給手続き、年金収入の管理 |
| 税金・公共料金の支払い | 固定資産税、住民税、光熱費の支払い |
| 各種手続きの代行 | 社会保険、介護保険などの手続き |
| 遺産分割協議 | 相続発生時の遺産分割協議への参加 |
身上監護
身上監護とは、本人の生活、健康、療養に関するサポートを行うことです。具体的には、下記のような業務が含まれます。
| 身上監護業務 | 具体例 |
|---|---|
| 医療に関する行為 | 入院手続き、医師との相談、治療方針の決定 |
| 介護に関する行為 | 介護サービス利用契約、介護施設入所手続き |
| 日常生活の支援 | 生活費の管理、買い物、公共サービスの利用手続き |
| 施設入所に関する行為 | 老人ホーム、介護施設への入所手続き |
職務内容に含まれないもの
任意後見人の役割は、あくまで本人の代理として法律行為を行うことであり、下記のような行為は含まれません。
- 直接的な介護や世話(食事介助、入浴介助など)
- 任意後見契約で定められていない行為
家庭裁判所への定期報告
任意後見人は、後見監督人を通じて、家庭裁判所に定期的に報告する義務があります。報告内容は、本人の状況、行った業務内容、財産状況などです。家庭裁判所は、報告内容を確認し、必要に応じて指示や助言を行います。
任意後見人の選び方
任意後見人は、信頼できる人を選ぶことが重要です。一般的には、家族や親族、友人、専門家(司法書士、弁護士など)が選ばれます。それぞれメリット・デメリットがあるので、下記の表を参考に、ご自身の状況に合った人を選びましょう。
| 種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 家族・親族・友人 | 信頼関係が築かれている、費用が抑えられる | 専門知識が不足している可能性、感情的な判断をしてしまう可能性 |
| 専門家 | 専門知識が豊富、客観的な判断ができる | 費用がかかる |
任意後見人になれない人
法律で下記に該当する人は、任意後見人になることができません。
- 未成年者
- 破産者
- 行方不明者
- 家庭裁判所から後見人、保佐人、補助人、未成年後見人を解任された人
- 本人に対して訴訟を起こしたことがある人、その配偶者と直系血族
- 不正な行為、著しい不行跡など、任意後見人にふさわしくない事由がある人
任意後見人の報酬
任意後見人の報酬は、任意後見契約で事前に決めておく必要があります。報酬額は、本人の財産状況、業務内容、任意後見人の役割などを考慮して決定します。家族や親族が無償で引き受けるケースもありますが、専門家(司法書士、弁護士)に依頼する場合は、月額3万円~別途費用が発生します。専門家に依頼する場合は、本人の判断能力が低下する前であっても費用が発生するケースもありますので、その他の支払条件を含めて、事前に確認することをお勧めします。
任意後見人の解任や辞任
任意後見契約は、将来の判断能力の低下に備えて、自身を守るための重要な制度です。しかし、状況の変化によっては、契約内容の見直しや後見人の変更が必要となるケースも出てきます。任意後見監督人の選任前は、いつでも任意後見契約の解除をすることにより任意後見人を解任することが可能です。ここでは、家庭裁判所の許可が必要になる後見監督人の選任後の、任意後見人の解任や辞任について、詳しく解説します。
任意後見人を解任できる事由
任意後見人は、本人の利益のために誠実に職務を遂行する義務を負っています。しかし、下記のような場合、家庭裁判所に申し立てを行い、任意後見人を解任することができます。
| 解任事由 | 具体例 |
|---|---|
| 不正行為 | 本人の財産の横領、私的流用、不正な処分 |
| 著しい不行跡 | 本人の財産管理を怠る、必要な契約を締結しない、身上監護を怠る |
| その他任務に適しない事由 | 心身の故障、行方不明、居住地の変更、本人との深刻な不和 |
任意後見人の解任を請求できるのは、以下の者です。
- 本人
- 任意後見監督人
- 四親等内の親族
- 検察官
任意後見人の辞任が認められる事由
任意後見人は、本人の同意や家庭裁判所の許可なく、勝手に辞任することはできません。辞任するためには、正当な事由があり、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
正当な事由として認められる例は下記のようになります。
| 辞任事由 | 具体例 |
|---|---|
| 心身の故障 | 病気や怪我により、後見事務を行うことが困難になった場合 |
| 居住地の変更 | 遠方への転居により、後見事務を行うことが困難になった場合 |
| 本人との不和 | 本人との関係が悪化し、後見事務を継続することが困難になった場合 |
| その他やむを得ない事由 | 介護負担、経済的な困難など |
辞任の申し立ては、任意後見人が家庭裁判所に行います。家庭裁判所は、辞任の事由が正当であると認め、かつ、本人の利益を害しないと判断した場合に、辞任を許可します。辞任が許可されると、後見人はその地位を失い、職務を行うことができなくなります。ただし、後任の任意後見人が選任されるまでの間、引き続き必要な事務を行う義務を負う場合があります。
任意後見監督人の役割について
任意後見人を監督する人のことを任意後見監督人といい、法定後見制度と違い、任意後見制度では後見監督人の選任が必須となります。
任意後見監督人とは
任意後見監督人の仕事は、任意後見人が任意後見契約の内容のとおりに適正に仕事をしているかを、監督することです。また、本人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行うときに、任意後見監督人が本人を代理します。任意後見監督人はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。
本人の判断能力が低下した段階で、任意後見人等は、家庭裁判所に申立てをします。申立てを受けた家庭裁判所は、任意後見監督人としてふさわしい人を選ぶことになりますが、任意後見監督人の仕事の内容から、本人の親族等ではなく、第三者(弁護士や司法書士など)が選ばれることが多くなります。任意後見監督人は、家庭裁判所に対し、定期的に報告をする義務も負っています。
任意後見監督人の職務内容
任意後見監督人の職務内容は下記の通りです。
| 役割 | 仕事内容 |
|---|---|
| 任意後見人の監督と家庭裁判所への報告 | 任意後見人が契約内容に従って職務を遂行しているか、本人の利益を害する行為をしていないかなど、任意後見人の事務を監督して定期的に家庭裁判所へ報告します。 |
| 任意後見人の職務代行 | 本人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行うときにや、任意後見人が死亡や病気などで職務を遂行できなくなった場合、一時的にその職務を代行します。 |
| 任意後見人の解任申立て | 任意後見人に不正行為や不行跡があった場合、家庭裁判所に解任を申し立てることができます。 |
任意後見監督人の報酬
任意後見監督人には、家庭裁判所が決定した報酬が支払われます。報酬額は、本人の財産状況などを考慮して決定されます。一般的には、月額1万円~3万円程度が相場となっています。
任意後見監督人の報酬は、任意後見制度を利用する上で必要な費用のひとつです。費用の負担が気になる方は、事前に専門家(司法書士や弁護士など)に相談し、詳しい説明を受けるようにしましょう。
まとめ
任意後見制度は、将来ご自身の判断能力が低下した場合に備え、あなたの意思を尊重し、適切なサポートを受けられるようにするための大切な仕組みです。任意後見制度の概要から、後見人の役割、手続きの流れ、メリット・デメリットまで解説しました。この記事を読めば、制度の全体像を理解し、ご自身にとって必要な準備を始めることができます。元気なうちに将来に備え、ご自身とご家族が安心して生活を送るために、ぜひこの記事を参考にしてください。
ルフレ司法書士事務所では、生前対策や認知症対策に関する様々な業務を扱っております。司法書士が、迅速丁寧にお客様の状況に合わせた最適なサポートを提供いたします。また、ご希望に応じて他士業(弁護士さんや税理士さん)を紹介しております。
全国対応していますので、お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。