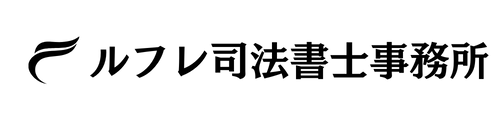認知症の相続人がいる場合の相続登記・手続きの完全ガイド
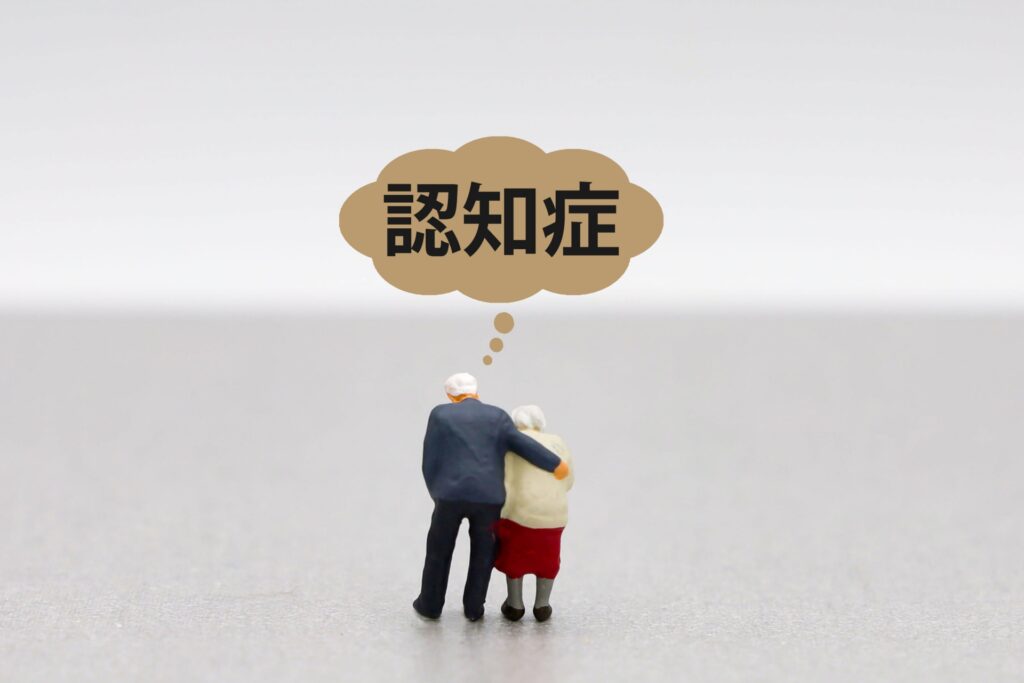
認知症の方が相続人になる場合、どのように手続きを進めれば良いのでしょうか? この記事では、認知症の相続人がいる場合の相続登記・手続きについて、成年後見制度の活用方法や、法定相続、相続人申告登記、遺言書による相続など、具体的な手続き方法を分かりやすく解説します。
また、相続登記の義務化の概要についても説明。さらに、認知症の相続に備えるための対策として、遺言書作成の重要性や、他の対策についても触れます。この記事を読むことで、認知症に関わる相続の不安を解消し、スムーズな手続きを実現するための知識を得ることができます。
相続登記の義務化と認知症
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。これにより、相続開始を知ってから3年以内に相続登記の申請を行わなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。この義務化は、2024年4月1日より前に開始した相続についても適用されます。法務省:相続登記の申請義務化特設ページ
認知症は、物事を判断する能力、いわゆる「意思能力」に影響を及ぼす病気です。認知症の方が相続人となった場合、相続手続きは複雑になり時間がかかるため、より迅速かつ適切な対応を求められることになります。
相続登記義務化の概要
相続登記の義務化は、所有者不明土地の増加による様々な問題に対処するために導入されました。これまでは相続登記は任意でしたが、今後は義務となります。放置すると、売却や担保設定などの手続きに支障が出るだけでなく、過料の対象となる可能性も出てきます。相続登記を行うことで、所有権を明確化し、円滑な不動産取引や管理を実現できます。
認知症の相続人がいる場合の相続手続き
認知症の相続人がいる場合、そのままでは遺産分割協議を行うことができないため、下記のいずれかの方法を選択することになります。
遺言書による相続手続き
被相続人(亡くなった方)が遺言書を残している場合、遺言書の内容に従って相続手続きが進められます。認知症の相続人がいても、遺言書があれば手続きを進めることができます。
【関連記事】
「相続トラブルを防ぐ!遺言書の基礎知識と正しい作り方ガイド」
「公正証書遺言作成を司法書士に依頼する場合の費用は?専門家ごとの違いを札幌の司法書士が解説」
法定相続分による登記手続き
相続人のなかに認知症の方がいても、法定相続分であれば手続きを進めることができます。ただし、この場合は不動産が相続人全員の共有となります。
法定相続分とは?
法定相続分とは、民法で定められた相続人の相続割合のことです。配偶者と子のいる場合は、配偶者が2分の1、子が2分の1を相続します。配偶者と親がいる場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1を相続します。
法定相続による登記の注意点
法定相続による登記では、不動産が共有状態になるため、将来の売却や活用に支障をきたす可能性があります。共有者全員の同意が必要となるため、意見が対立すると手続きが難航する可能性があります。また、共有者の数が多くなると、管理も複雑になります。
【関連記事】
「家族で話す前に知っておきたい法定相続分の基本|誰がどのくらい相続できるのかを徹底解説」
成年後見制度の利用
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人のために、後見人等を選任し、財産管理や法的行為をサポートする制度です。認知症の相続人がいる場合、この制度を利用することで、遺産分割協議を行い、特定の相続人に相続財産を移転することができます。
成年後見制度とは?
成年後見制度は、家庭裁判所が後見人等を選任する制度で、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
成年後見人の選任方法
成年後見人の選任は、家庭裁判所で行います。申立ができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長などです。選任の際には、本人の意思を尊重し、本人の利益を守ることを最優先に考慮します。後見人には、親族、弁護士、司法書士が選任されることが多いです。
成年後見制度を利用する場合の注意点
成年後見制度は、原則として利用を開始するとご本人が亡くなるまで終了しません。成年後見人として弁護士や司法書士が選ばれた場合、毎月2万〜5万円の報酬が発生し、この費用を支払い続けなくてはいけなくなります。なお、この成年後見制度については、現在見直しが検討され2026年の改正が予定されているため、今後は期間限定での利用ができるようになる可能性があります。
相続人申告登記
相続人申告登記とは、被相続人が死亡し、誰が相続人であるかを法務局に申告する手続きです。この登記を行うことで、相続登記の義務を果たしたことにはなりませんが、過料の対象からは除外されるため、3年以内に相続登記ができない場合、相続人申告登記を行うことで、過料を回避できます。これは、将来の相続登記に向けた準備的な手続きです。 法務省:相続人申告登記について
認知症の相続に備える対策
ここまで、既に認知症の相続人がいる場合の相続手続きについて解説しましたが、事前の対策をしたいと考える方もいらっしゃるかと思います。認知症の相続に備えるためには、以下の4つの対策が考えられます。
遺言書の作成
認知症の相続人がいる場合でも、遺言書が残されていれば、遺言書の内容のとおりに手続きを進めることができます。遺言書には、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割したり、特定の相続人に特定の財産を相続させることができます。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。それぞれ作成方法に違いがあるので、自分に合った方法を選択しましょう。
遺言書の種類と特徴
| 種類 | 作成方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 全文を自筆で書く | 費用がかからない 手軽に作成できる | 家庭裁判所による検認が必要 紛失・改ざんの恐れがある 形式の不備で無効になる場合がある |
| 公正証書遺言 | 公証役場で作成 | 家庭裁判所による検認が不要 紛失・改ざんの心配がない 形式の不備がない | 費用がかかる |
| 秘密証書遺言 | 遺言書を封じて公証役場に提出 | 内容を秘密にできる | 家庭裁判所による検認が必要 費用がかかる |
遺言書を作成する際は、それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分に合った方法を選ぶことが大切です。また、2020年から法務局による自筆証書遺言の保管制度(法務省:自筆証書遺言書保管制度について)が始まりました。この制度を利用することにより家庭裁判所による検認が不要となり、費用も高くないため弊所ではおすすめしています。いずれの方法を選択する場合でも、専門家(司法書士や弁護士など)に相談しながら作成することをおすすめします。
【関連記事】
「相続トラブルを防ぐ!遺言書の基礎知識と正しい作り方ガイド」
「公正証書遺言作成を司法書士に依頼する場合の費用は?専門家ごとの違いを札幌の司法書士が解説」
生前贈与
将来、相続財産となる予定の不動産や預貯金を予め贈与する方法もあります。この方法を生前贈与といい、こちらも認知症対策として利用されます。
【関連記事】
「不動産を生前贈与するメリット・デメリットは?税金や手続きを分かりやすく解説」
家族信託
家族信託は、信頼できる家族に財産管理を任せることができる制度です。認知症になる前に、財産の管理や処分を委託しておくことで、手続きをスムーズに進めることができ、相続財産を誰に取得させるかも指定することもできます。また、家族信託は、遺言では実現できないような柔軟な財産管理が可能である点もメリットです。
家族信託のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 柔軟な財産管理が可能 認知症対策や相続対策で利用できる | 信託契約の作成に費用がかかる 専門家のサポートが必要になる |
家族信託は、成年後見制度と比較して柔軟な財産管理が可能ですが、信託契約の作成には専門家のサポートが必要となる場合があり、費用もかかります。家族信託の利用を検討する際は、専門家(司法書士や弁護士など)に相談することをおすすめします。
【関連記事】
「家族信託の活用事例:あなたの家族に最適な方法の見つけ方」
任意後見契約
任意後見契約は、ご本人が認知症になった場合に備えて、将来、後見人になって欲しい人との間で、予め契約書を締結しておく制度のことをいいます。ご本人が判断能力が低下した段階で家庭裁判所に申立てを行うと後見監督人が選任され、後見人が任意後見を開始することになります。ご本人が相続人となる場合でも、予め後見人がいるため、相続発生後に成年後見制度の利用して手続きするよりも、スムーズに相続手続きをすることができます。
【関連記事】
「任意後見制度とは?家族が知っておくべき基本情報」
まとめ
認知症の方が相続人となる場合、相続手続きは複雑になり、通常より多くの時間と費用を要することがあります。特に、相続登記の義務化により、期限内に手続きを完了させる必要性が高まっています。放置すると過料の対象となる可能性もあるため、早めの対応が重要です。
認知症の相続人がいる場合の相続手続きの方法はいくつかありますが、それぞれの方法のメリット・デメリットを理解し、状況に応じて適切な方法を選択することが大切です。また、将来の相続トラブルを避けるためには、事前の対策が不可欠です。認知症と相続の問題は複雑ですが、この記事で紹介した内容を参考に、適切な準備と対応を行うことで、将来のトラブルを未然に防ぐことが可能です。
ルフレ司法書士事務所では、相続手続きをはじめ、生前対策や認知症対策に関する様々な業務を扱っております。司法書士が、迅速丁寧にお客様の状況に合わせた最適なサポートを提供いたします。また、ご希望に応じて他士業(弁護士さんや税理士さん)を紹介しております。
全国対応していますので、お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。