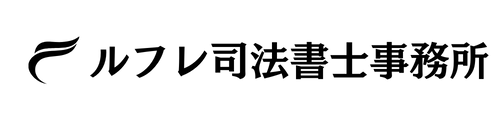【最新版】抵当権抹消登記を自分で!費用削減と最短完了の秘訣

住宅ローン完済後の抵当権抹消登記、費用を抑えるなら自分で手続きをすることもできます。この記事を読めば、必要書類の揃え方から登記申請書の具体的な書き方、法務局への申請方法まで、専門知識がなくても迷わず進められる全手順がわかります。最短で手続きを終えるための秘訣を、初めて手続きをする方向けに徹底解説します。
抵当権抹消登記は自分でできる?司法書士に依頼した場合との比較
住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消登記に関する書類が送られてきます。この手続きは、法務局で不動産登記簿から抵当権の抹消するための重要な手続きです。多くの方が「専門家に任せるもの」と考えがちですが、結論から言うと、抵当権抹消登記はご自身で行うことが可能です。
ただし、ご自身で行う場合と、司法書士に依頼する場合とでは、それぞれにメリット・デメリットが存在します。ご自身の状況に合わせて最適な方法を選ぶために、まずは両者の違いを正確に理解しましょう。
自分で抵当権抹消登記を行うメリットとデメリット
ご自身で手続きを進める最大の魅力は、やはり費用の節約です。しかし、その分手間や時間がかかることも覚悟しておく必要があります。
メリット
- 費用を大幅に節約できる
司法書士に支払う報酬(手数料)が一切かかりません。一般的に2万円~4万円程度かかるこの費用を節約できるのは、最大のメリットと言えるでしょう。
デメリット
- 手間と時間がかかる
必要書類の準備や登記申請書の作成、管轄法務局への問い合わせ等など、すべて自分で行う必要があります。特に、法務局の窓口が開いているのは平日の日中のみのため、お仕事をされている方は時間を確保するのが難しい場合があります。 - 書類の不備(補正)のリスクがある
慣れない作業のため、書類の記載ミスや添付書類の不足といった不備が生じがちです。不備があると、法務局から修正(補正)を指示され、再度法務局へ出向かなければならないこともあります。 - 複雑なケースでは対応が難しい
登記簿上の金融機関の名称や住所と現在の名称や現住所が異なる、結婚などで氏名が変わっている、相続が発生しているといったケースでは、追加の書類が必要となり手続きが複雑化します。このような場合、個人で対応するのは難易度が高くなります。
司法書士に依頼するメリットとデメリット
司法書士は登記の専門家です。費用はかかりますが、その分、確実性と安心感を得られます。
メリット
- 手続きが正確かつスピーディー
専門家であるため、書類作成から申請までミスなく迅速に進めてくれます。書類の不備で手続きが滞る心配はほとんどありません。 - 手間と時間を一切かけずに済む
金融機関から受け取った書類を司法書士に渡し、委任状に署名・押印するだけで、後の手続きはすべて代行してくれます。平日に法務局へ行く必要もなく、ご自身の時間を有効に使えます。 - 複雑な案件でも安心して任せられる
住所変更や相続などが絡む複雑なケースでも、必要な手続きをすべて洗い出し、適切に対応してくれます。書類を紛失してしまった場合など、イレギュラーな事態にも対応可能です。
デメリット
- 費用(報酬)がかかる
司法書士に依頼する場合、登録免許税などの実費に加えて、2万円~4万円程度の報酬(手数料)がかかります。これが唯一にして最大のデメリットです。
自分で手続きするかどうかの判断基準
結局のところ、自分で手続きすべきか、司法書士に依頼すべきかは、ご自身の状況によって異なります。以下の比較表を参考に、どちらがご自身に向いているか判断してみてください。
特に重要な判断ポイントは、「平日の日中に時間が取れるか」と「登記簿上の情報(住所・氏名)に変更がないか」の2点です。これらがクリアできれば、ご自身で挑戦してみる価値は十分にあります。
| 判断基準 | 自分でやるのがおすすめな人 | 司法書士への依頼がおすすめな人 |
|---|---|---|
| 費用 | 少しでも費用を安く抑えたい | 多少費用がかかっても、確実性を重視したい |
| 時間と手間 | 平日の日中に法務局へ行く時間が取れる 書類作成などの事務作業が苦にならない | 仕事や家事で忙しく、平日に時間が取れない 面倒な手続きは専門家に任せたい |
| 手続きの難易度 | 登記簿上の住所・氏名から変更がない 相続など特殊な事情がない | 登記簿上の住所・氏名が変わっている 相続が発生している 書類を紛失したなど、複雑な事情がある |
| 安心感 | 多少の不備や修正も自分で対応できる | ミスなく確実に手続きを完了させたい 手続きに関する不安をなくしたい |
もし、ご自身で手続きを進める中で少しでも不安を感じたり、難しいと感じたりした場合は、無理をせずに途中からでも司法書士に相談することをおすすめします。
抵当権抹消登記を自分で行う場合の費用内訳
住宅ローンを完済し、抵当権抹消登記を検討する際、多くの方が気になるのが「費用」ではないでしょうか。専門家である司法書士に依頼せず、自分で手続きを行う最大のメリットは、この費用を大幅に節約できる点にあります。ここでは、自分で抵当権抹消登記を行う際に実際にどれくらいの費用がかかるのか、その内訳を詳しく解説します。司法書士に依頼した場合との比較も行い、どれだけお得になるのかを具体的に見ていきましょう。
必ずかかる費用「登録免許税」
抵当権抹消登記を申請する際に、必ず国に納めなければならない税金が「登録免許税」です。これは、登記手続きの手数料として法務局に納付するもので、自分で手続きする場合でも、司法書士に依頼する場合でも同額が発生します。
登録免許税は、現金で直接支払うのではなく、税額分の「収入印紙」を購入し、登記申請書に貼り付けて納付するのが一般的です。収入印紙は、法務局内の印紙販売窓口や、大きめの郵便局などで購入できます。申請書を提出する直前に法務局で購入するとスムーズです。
登録免許税の計算方法
抵当権抹消登記の登録免許税は、非常にシンプルで、以下の計算式で算出されます。
登録免許税 = 不動産の個数 × 1,000円
ここでいう「不動産の個数」とは、抵当権が設定されている土地や建物の数のことです。数え方には少し注意が必要です。
- 一戸建ての場合:通常、「土地1筆」と「建物1棟」で構成されるため、不動産の個数は「2個」となります。この場合の登録免許税は2,000円です。
- マンションの場合:「専有部分の建物1個」と、その建物が建っている「敷地権の数(土地の筆数)」を合計します。例えば、敷地が2筆の土地にまたがって建っているマンションであれば、「建物1個+土地2筆」で不動産の個数は「3個」となり、登録免許税は3,000円です。
- 不動産の個数の確認方法:正確な個数は、法務局で取得できる「登記事項証明書(登記簿謄本)」で確認できます。不動産の表示欄を見れば、土地が何筆あるか、建物が何個あるかが記載されています。
なお、抵当権が設定されている不動産が20個を超える場合、登録免許税の上限は20,000円と定められています。
その他の実費(書類取得費用など)
登録免許税の他に、手続きの過程で必要となる費用がいくつかあります。これらは「実費」と呼ばれ、状況に応じて発生します。主な実費は以下の通りです。
| 費用項目 | 費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 登記事項証明書(登記簿謄本)の取得費用 | 1通 480円~600円 | 登記内容の事前確認や、登記完了後の確認のために取得します。法務局窓口での請求は600円、オンライン請求・郵送受取は520円、オンライン請求・窓口受取は490円です。 |
| 住民票または戸籍の附票の取得費用 | 1通 300円前後 | 登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合は、抵当権抹消登記の前提として住所変更登記をする必要があります。市区町村役場で取得します。手数料は自治体により異なります。 |
| 郵送費 | 500円~1,000円程度 | 法務局へ郵送で申請する場合に必要です。大切な書類のため、往復ともに書留郵便を利用するのが一般的です。登記完了後の書類を返送してもらうための返信用封筒と切手も同封します。 |
| 交通費 | 実費 | 法務局の窓口へ直接出向いて申請や相談をする場合の交通費です。 |
これらの実費を合計しても、通常は1,000円から3,000円程度に収まることがほとんどです。
自分で登記した場合と司法書士に依頼した場合の費用比較
それでは、自分で手続きした場合と司法書士に依頼した場合で、総費用にどれくらいの差が出るのでしょうか。一般的な一戸建て(土地1筆、建物1棟)のケースで比較してみましょう。
| 費用項目 | 自分で手続きする場合 | 司法書士に依頼する場合(目安) |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 2,000円 | 2,000円 |
| その他実費(書類取得・郵送費など) | 約2,000円 | 約2,000円 |
| 司法書士報酬 | 0円 | 20,000円~40,000円 |
| 合計費用 | 約4,000円 | 約24,000円~44,000円 |
上記の比較表からわかる通り、自分で抵当権抹消登記を行えば、司法書士に支払う報酬(2万円~4万円程度)が節約できます。手続き自体は、書類の準備と法務局への申請が中心で、平日に時間を確保できる方であれば自分で行うことが可能です。この費用差を考慮し、ご自身で挑戦してみる価値は十分にあると言えるでしょう。
最短4ステップ!自分で抵当権抹消登記を行う手順と流れ
住宅ローンを完済したら、不動産に設定されている「抵当権」を抹消するための登記手続きが必要です。この手続きは、司法書士に依頼するのが一般的ですが、ご自身で行うことも可能です。自分で手続きを進めれば、司法書士への報酬を節約できます。
一見、難しそうに感じるかもしれませんが、手順を一つひとつ確認しながら進めれば、決して不可能な手続きではありません。ここでは、抵当権抹消登記を自分で行うための全体像を、最短4ステップで分かりやすく解説します。
まずは、以下の表で大まかな流れを掴みましょう。
| ステップ | 主な作業内容 | 場所・相手 | ポイント |
|---|---|---|---|
| ステップ1 | 必要書類の受け取り | 金融機関(銀行など) | 完済後、自動的に送られてくる場合と、連絡が必要な場合があります。 |
| ステップ2 | 登記申請書の作成と準備 | 自宅等 | 法務局のウェブサイトでテンプレート(テンプレートはこちら)を入手し、記入例を参考に作成します。 |
| ステップ3 | 登記申請 | 管轄の法務局 | 窓口持参、郵送、オンラインのいずれかの方法で申請します。 |
| ステップ4 | 登記完了後の書類受け取り | 管轄の法務局 | 通常申請から1〜2週間で登記が完了。完了書類を受け取ります。 ※権利証を紛失した場合、完了まで+1〜2週間程かかります。 |
この4つのステップを順番にこなしていくことで、ご自身での抵当権抹消登記が完了します。次の項目から、各ステップで具体的に何を行うのかを詳しく見ていきましょう。
【参考情報】
法務局:住宅ローン等を完済した方へ(抵当権の登記の抹消手続のご案内)
ステップ1 金融機関から必要書類を受け取る
住宅ローンの完済手続きが完了すると、借入先の金融機関(銀行や信用金庫など)から抵当権抹消登記に必要な書類一式が送られてきます。通常、完済後1〜2週間程度で自宅に届きますが、金融機関によっては別途申し出が必要な場合もあります。もし完済後しばらく経っても書類が届かない場合は、一度金融機関の担当窓口に問い合わせてみましょう。
このとき受け取る書類の中には、再発行ができないものもあります。絶対に紛失しないよう厳重に保管してください。特に「登記識別情報(または登記済証)」は、不動産の権利に関する最も重要な書類の一つです。
具体的にどのような書類が送られてくるかについては、後の章「【ステップ1】抵当権抹消登記の必要書類を揃える」で詳しく解説します。
ステップ2 登記申請書を作成しその他の書類を準備する
金融機関から書類が届いたら、次にご自身で「抵当権抹消登記申請書」を作成します。この申請書が、法務局へ手続きを依頼するためのメインの書類となります。
登記申請書は、法務局のウェブサイトからWord形式のテンプレート(テンプレートはこちら)をダウンロードして作成するのが便利です。記載する内容は、不動産の情報や金融機関の情報など、手元にある書類を見ながら転記するものがほとんどです。詳しい書き方については、後の章「【ステップ2】抵当権抹消登記申請書の書き方を徹底解説」で一つひとつ丁寧に説明しますのでご安心ください。
この段階で、金融機関から受け取った書類と自分で作成・取得した書類がすべて揃っているか、念入りに確認しましょう。
全国の法務局では、登記手続に関する専門的な知識をお持ちでないという方に対して、登記手続案内として、登記申請書の作成等に必要な情報の提供を行っています。
詳しくは下記のリンク「法務局:登記手続案内」をご参照ください。
【参考情報】
法務局:登記手続案内
ステップ3 管轄の法務局へ登記申請を行う
すべての書類が揃ったら、いよいよ法務局へ登記申請を行います。ここで注意すべき点は、どの法務局でも申請できるわけではなく、対象となる不動産の所在地を管轄する法務局に申請する必要があるという点です。
管轄の法務局は、法務局のウェブサイトで簡単に調べることができます。申請方法は、主に以下の3つです。
- 窓口申請:法務局の窓口へ直接書類を持参する方法です。書類に不備がないかその場で相談・確認してもらえる可能性があるため、初めての方には最も安心な方法です。
- 郵送申請:完成した書類一式を、管轄の法務局へ郵送(書留郵便またはレターパックプラス)する方法です。平日に法務局へ行く時間がない方に便利です。
- オンライン申請:「登記・供託オンライン申請システム」を利用してインターネット経由で申請する方法です。専用ソフトのインストールや電子署名の準備が必要で、PC操作に慣れている方向けです。
ご自身の状況に合わせて最適な申請方法を選びましょう。どの方法で申請するかによって、準備物や手順が少し異なりますので、後の章「【ステップ3】管轄法務局への申請方法」でそれぞれの詳細を確認してください。
ステップ4 登記完了後に書類を受け取る
法務局に申請書類を提出したら、登記が完了するのを待ちます。申請内容に不備(補正)がなければ、通常1週間から2週間程度で手続きは完了します。完了までの期間は、法務局の混雑状況によって変動します。※「登記識別情報(または登記済証)」を紛失等の理由により法務局に提出できない場合、完了まで+1〜2週間程かかります。
登記が完了すると、法務局から以下の書類が交付されます。
- 登記完了証:登記手続きが完了したことを証明する書類です。
- 原本還付書類:原本還付を請求した場合は、その書類が返却されます。
これらの書類の受け取り方法は、法務局の窓口で直接受け取るか、郵送で送ってもらうかのどちらかです。郵送を希望する場合は、申請時に切手を貼った返信用封筒(またはレターパックプラス)を一緒に提出しておく必要があります。
最後に、登記が間違いなく抹消されたかを確認するため、「登記事項証明書(登記簿謄本)」又は「登記情報」を1通取得することをおすすめします。証明書を取得し、抵当権の記載が消えていることをご自身の目で確認できれば、すべての手続きは無事終了です。
【ステップ1】抵当権抹消登記の必要書類を揃える
抵当権抹消登記を自分で行うための最初のステップは、必要書類を正確に揃えることです。書類は大きく分けて「金融機関から受け取るもの」と「自分で用意・作成するもの」の2種類があります。住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹失に必要な書類一式が送られてくるのが一般的ですが、万が一届かない場合は金融機関へ連絡しましょう。ここでは、それぞれの書類について詳しく解説します。
金融機関から受け取る重要書類一覧
住宅ローンを完済すると、通常1週間から3週間ほどで、金融機関から抵当権抹消登記に必要な重要書類が郵送されてきます。これらの書類は、再発行が難しいものも含まれるため、届いたらすぐに中身を確認し、すべて揃っているかチェックしましょう。紛失しないよう、法務局へ申請に行くまで大切に保管してください。
登記識別情報(または登記済証)
「登記識別情報」または「登記済証」は、その不動産の権利者であることを証明する非常に重要な書類です。一般的に「権利証」と呼ばれるものがこれにあたります。
平成17年(2005年)の不動産登記法改正までは、抵当権設定登記を行った場合に朱色の「登記済」の印が押された「登記済証」が発行されていました。平成17年(2005年)の不動産登記法改正を境に形式が変わり、現在では12桁の英数字のパスワードが記載された「登記識別情報通知」が発行されています。どちらの形式でも手続き上の効力は同じです。金融機関で保管されていた権利証が、ローン完済に伴い返還されます。
登記原因証明情報(解除証書など)
「登記原因証明情報」とは、住宅ローンを全額返済したことにより、抵当権が消滅したという事実(登記原因)を証明するための書類です。金融機関によって「解除証書」「弁済証書」「放棄証書」など名称が異なる場合がありますが、役割は同じです。
この書類には、抵当権者(金融機関)、債務者(あなた)、対象不動産の情報などが記載されていますので、内容に間違いがないか確認しておきましょう。
金融機関の委任状
この委任状は、抵当権者である金融機関が、不動産の所有者(あなた)又はの所有者(あなた)の代理人に抵当権抹消登記の手続きを委任することを証明する書類です。通常、金融機関の代表者名と法人の実印が押印されています。
自分で用意・作成する書類一覧
金融機関から受け取る書類に加えて、ご自身で準備・作成する必要がある書類もあります。特に「抵当権抹消登記申請書」は、ご自身で一から作成する中心的な書類となります。
| 書類名 | 入手先・作成者 | 備考 |
|---|---|---|
| 抵当権抹消登記申請書 | 自分で作成 | 法務局のウェブサイトからテンプレート(テンプレートはこちら)を入手します。書き方は次の章で詳しく解説します。 |
| 住民票の写し または 戸籍の附票 | 市区町村役場 | 登記簿上の住所と現住所が異なる場合のみ必要です。マイナンバー記載のないものを取得します。 |
| (推奨)登記事項証明書又は登記情報 | 法務局 | 申請書に不動産の情報を正確に記入するために事前に取得しておくと安心です。 |
抵当権抹消登記申請書
法務局へ抵当権抹消を申請するためのメインとなる書類です。この申請書に、不動産の情報、登記の目的、原因、権利者・義務者の情報などを正確に記入する必要があります。申請書の様式(テンプレート)は、管轄の法務局のウェブサイト(テンプレートはこちら)からダウンロードできます。具体的な書き方や注意点については、次の「ステップ2」で詳しく解説しますので、ご安心ください。
住民票(登記上の住所と現住所が違う場合)
住宅ローンを組んで抵当権を設定した時から、引っ越しなどで住所が変わっている場合は、抵当権抹消登記の前提として住所変更登記をする必要があります。もし複数回引っ越しをしていて住民票だけでは住所の変遷が追えない場合は、前住所地が記載された「戸籍の附票」が必要になります。
なお、法務局に提出する住民票は、マイナンバー(個人番号)の記載がないものを取得するようにしてください。
【ステップ2】抵当権抹消登記申請書の書き方を徹底解説
抵当権抹消登記を自分で行う上で、最も重要な作業が「登記申請書」の作成です。専門用語が多く難しそうに感じますが、ポイントさえ押さえれば誰でも作成できます。この章では、テンプレートの入手方法から、各項目の具体的な書き方、書類のまとめ方まで、一つひとつ丁寧に解説します。
登記申請書テンプレートの入手方法
登記申請書のテンプレート(様式)は、法務局のウェブサイト(テンプレートはこちら)から無料でダウンロードするのが最も確実で便利です。手書き用のPDF形式と、パソコンで直接入力できるWord形式の両方が用意されています。
法務局のウェブサイト内にある「不動産登記の申請書様式について」のページから、「抵当権抹消登記申請書」を探してください。多くの場合、詳しい記載例もセットでダウンロードできるため、そちらも必ず確認しましょう。
登記申請書の各項目の書き方と記入例
ダウンロードしたテンプレートに、必要事項を記入していきます。パソコンで作成しても、手書きでもどちらでも構いません。ここでは、特に間違いやすい項目を中心に、書き方のポイントを解説します。
登記申請書は、登記簿に記載されている情報を元に正確に記入する必要があります。お手元に不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を用意して、見比べながら作業を進めるとスムーズです。
原因と日付の書き方
「登記の目的」の下にある「原因」の欄には、抵当権が消滅した理由とその日付を記載します。この情報は、金融機関から受け取った「登記原因証明情報(解除証書、弁済証書など)」に記載されている文言と日付をそのまま転記します。
- 原因: 「解除」「弁済」など、登記原因証明情報に記載の文言を記入します。
- 日付: 住宅ローンを完済した日です。こちらも登記原因証明情報に記載されています。元号から正確に記入しましょう。
【記入例】
原因 令和○年○月○日弁済
権利者と義務者の書き方
次に、申請する人の情報を記載します。「権利者」は抵当権を抹消して権利を得る人(不動産所有者であるあなた)、「義務者」は抵当権を失う側(お金を貸していた金融機関)を指します。
この情報も、登記事項証明書や金融機関から受け取った書類を見ながら、正確に記入することが重要です。
| 項目 | 権利者(あなた) | 義務者(金融機関) |
|---|---|---|
| 住所 | 登記事項証明書に記載されているあなたの住所を記入します。 | 金融機関の代表者事項証明書などに記載されている本店所在地を記入します。 |
| 氏名・名称 | あなたの氏名を記入します。 | 金融機関の正式名称(商号)を記入します。 |
| その他 | 申請人の欄には、住所氏名を記入し、押印(認印で可)も忘れずにします。書類に不備があった際に法務局から連絡があるため、連絡先の電話番号も記入します。 | 代表者の資格(例:代表取締役)と氏名を記入します。 |
【注意点】
- 権利者であるあなたの現在の住所が、登記簿上の住所と異なる場合は、抵当権抹消登記の前提として「登記名義人住所変更登記」が別途必要になります。
- 義務者である金融機関の情報は、受け取った書類(資格証明書など)の通り、一字一句間違えずに記入してください。
添付情報(添付書類)の書き方
「添付情報」の欄には、申請書と一緒に法務局へ提出する書類の名称をすべて記載します。これは、提出書類のチェックリストの役割も果たします。
【記入例】
添付情報 登記識別情報(又は登記済証) 登記原因証明情報 会社法人等番号 代理権限証明情報
【各書類の説明】
- 登記識別情報(又は登記済証): 抵当権設定時に金融機関が預かっていた権利証のことです。
- 登記原因証明情報: 金融機関から受け取る「解除証書」などの書類です。
- 会社法人等番号: 金融機関の会社法人等番号を記載すれば、原則としてその金融機関の登記事項証明書(代表者事項証明書)の添付を省略できます。番号は金融機関から受け取る書類に記載されています。
- 代理権限証明情報: 金融機関からあなたへの「委任状」のことです。
登録免許税と収入印紙の貼り方
登記申請には、登録免許税という税金を納める必要があります。抵当権抹消登記の場合、登録免許税は「不動産1個につき1,000円」です。
- 一戸建ての場合: 「土地」と「建物」で不動産は2個なので、2,000円。
- マンションの場合: 「専有部分(建物)」と「敷地権の数(土地)」を合計した個数×1,000円となります。例えば敷地権が2つあれば、建物1個+土地2個で合計3個、3,000円です。
計算した税額分の収入印紙を購入し、A4の白紙(「印紙貼付台紙」と記載)に貼り付けます。登記申請書とホッチキス止めし、契印も忘れずにします。
【最重要注意点】
貼り付けた収入印紙には、絶対に自分で割印(消印)をしないでください。消印は法務局の職員が行います。誤って消印してしまうと、再購入が必要になる場合があります。
書類をまとめる際の注意点(ホチキス留めの順番)
すべての書類が準備できたら、順番通りに重ねてホチキスで綴じます。この順番は厳密な決まりではありませんが、法務局が確認しやすいように整えるのが一般的です。以下の順番でまとめるとスムーズです。
- 登記申請書(収入印紙を貼ったもの。別紙の場合は印紙貼付台紙を次につづる)
- 登記原因証明情報(解除証書など)
- 金融機関からの委任状(代理権限証明情報)
書類は左側を2箇所ほどホチキスで留めます。上記1が複数枚にわたる場合は、ページの綴じ目に申請書に押印したのと同じ印鑑で「契印」を押してください。これにより、書類が一体のものであることを証明します。
【ステップ3】管轄法務局への申請方法
抵当権抹消登記の申請書類がすべて完成したら、いよいよ法務局へ提出します。申請方法は大きく分けて「窓口」「郵送」「オンライン」の3つがあります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、ご自身の状況に合わせて最適な方法を選びましょう。初めての方で時間に都合がつく場合は、その場で相談や不備の確認ができる窓口申請が最も安心です。
管轄の法務局の調べ方
抵当権抹消登記の申請先は、どこの法務局でも良いわけではありません。必ず、対象となる不動産の所在地を管轄する法務局に申請する必要があります。ご自身の現住所の最寄りの法務局ではない点に注意してください。
管轄の法務局は、法務局の公式ウェブサイト(法務局:管轄のご案内)で簡単に調べることができます。
- 法務局のウェブサイトにある「管轄のご案内」ページにアクセスします。
- 「管轄を探す」又は「地図から探す」で検索します。
- 検索結果に表示された法務局が、申請先となります。
登記事項証明書(登記簿謄本)や登記情報に記載されている土地の「所在」や建物の「所在」の住所を元に検索してください。
法務局の窓口で申請する方法
法務局の窓口に直接出向いて申請する方法です。書類に不備がないか不安な方や、手続きに不明点がある方に最もおすすめの方法です。
窓口申請のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 法務局や担当者にもよるが、軽微な内容であれば、その場で質問をしたり、書類の修正ができる場合がある。 | 法務局の開庁時間(通常は平日の午前9時00分~午後5時00分)に行く必要がある。 |
| 混雑している場合、待ち時間が発生することがある。 | |
| 法務局が遠い場合、交通費や移動時間がかかる。 |
当日の持ち物と流れ
法務局へ行く際の持ち物は以下の通りです。忘れ物がないように事前にチェックしましょう。
- 登記申請書一式:ホチキスで綴じた完成版の書類
- 登録免許税分の収入印紙:事前に郵便局などで購入するか、法務局内の印紙売店で購入します。
- 申請人の印鑑:申請書に押印したものと同じ印鑑(認印で可)。書類の訂正(補正)で必要になる場合があります。
- (任意)登記申請書のコピー:提出する申請書一式のコピーを持参すると、それに受付印を押してもらえ、控えとして保管できます。
郵送で申請する方法
平日に法務局へ行く時間がない方や、管轄の法務局が遠方にある場合に便利な方法です。
郵送申請のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 法務局の開庁時間に関係なく、いつでも発送できる。 | その場で質問ができない。 |
| 遠方の法務局へも交通費をかけずに申請できる。 | 法務局に申請書が到着した日が「申請日」となるため、窓口申請よりも完了が遅くなる場合がある。 |
郵送する際の注意点
郵送で申請する場合は、以下の点に注意してください。
- 封筒の準備:角形2号(A4サイズが折らずに入る大きさ)の封筒を用意します。
- 宛名の記載:管轄法務局の「不動産登記部門 御中」などと記載します。
- 朱書き:封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と赤字で必ず記載してください。
- 郵送方法:普通郵便は絶対に使用せず、必ず郵便物の追跡が可能な「書留郵便」または「レターパックプラス」で送付します。これは、登記識別情報などの重要書類が含まれているためです。
- 返信用封筒の同封:登記完了後に「登記完了証」や「登記識別情報通知書」を送り返してもらうための返信用封筒またはレターパックプラスを同封します。返信用封筒にはご自身の住所・氏名を記載し、簡易書留分の切手(基本料金+簡易書留料金)を貼っておきましょう。
郵送申請の場合、法務局に申請書が到着した日が「申請日」となります。
オンラインで申請する方法(登記・供託オンライン申請システム)
法務省が提供する「登記・供託オンライン申請システム」を利用して、インターネット経由で申請する方法です。自宅のパソコンから平日の午前8時30分から午後9時まで申請が可能ですが、初めての方には若干ハードルが高い方法といえます。
オンライン申請のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 平日の午前8時30分から午後9時まで、自宅等から申請できる。 | マイナンバーカードやICカードリーダライタの準備、専用ソフトのインストールなど、事前の準備と初期費用が必要。 |
| 登録免許税を電子納付(インターネットバンキング等)できる。 | システムを操作するため、初めての方には一定の難易度がある。 |
| 交通費がかからない。 | 登記原因証明情報などの添付書類は、別途法務局へ郵送または持参する必要がある(特例方式)。 |
オンライン申請は、マイナンバーカードとICカードリーダライタを用意し、法務省のウェブサイトから「申請用総合ソフト」をダウンロード・インストールして行います。申請情報を作成・送信した後、金融機関から受け取った登記原因証明情報などの原本は、申請日を除く2日以内に管轄法務局へ別途郵送または持参する必要があります。
このように、オンライン申請は便利ですので、システム操作が得意な方は挑戦してみる価値はあると思います。それ以外で、初めて自分で抵当権抹消登記を行う方には、窓口申請または郵送申請をおすすめします。
自分で抵当権抹消登記を行う際の注意点とよくある質問
抵当権抹消登記を自分で行う際、多くの方がつまずきやすいポイントや疑問点があります。ここでは、手続きをスムーズに進めるための注意点と、よくある質問への回答をまとめました。事前に確認しておくことで、予期せぬトラブルや手戻りを防ぎましょう。
住宅ローン完済後いつまでに手続きすべきか
住宅ローンを完済しても、抵当権抹失登記の申請には法律上の明確な期限は設けられていません。しかし、手続きを先延ばしにすると様々なデメリットが生じる可能性があるため、金融機関から必要書類が届き次第、速やかに行うことを強く推奨します。
長期間放置した場合の主なリスクは以下の通りです。
- 不動産の売却ができない:抵当権が付いたままの不動産は、買主が見つかりません。売却を決めた際に、慌てて手続きをすることになります。
- 新たな融資の担保にできない:その不動産を担保に新たなローンを組む際、抵当権が残っていると審査に影響が出ます。
- 手続きの複雑化:金融機関の合併や商号変更、代表者の交代などがあった場合、それを証明するための追加書類が必要になり、手続きが煩雑になることがあります。
- 書類の紛失:金融機関から受け取った重要書類を紛失してしまうリスクが高まります。書類によっては再発行が難しく、余計な手間と費用がかかる原因となります。
完済したという安心感から後回しにしがちですが、将来のトラブルを避けるためにも、なるべく早く手続きを完了させましょう。
登記上の住所や氏名が変わっている場合はどうする?
住宅ローン契約時から現在までに、引越しによる住所変更や、結婚・離婚による氏名変更があった場合、抵当権抹消登記の前提として「登記名義人住所氏名変更登記」を申請する必要があります。これは、登記簿上の所有者の情報(住所・氏名)を現在のものに変更する手続きです。
この登記名義人住所氏名変更登記は、抵当権抹消登記と同時に(連件で)申請するのが一般的です。申請書は「登記名義人住所氏名変更」と「抵当権抹消」の2通を作成し、まとめて法務局に提出します。
変更内容に応じて、以下の書類と費用が別途必要になります。
| 変更内容 | 必要な追加書類 | 別途かかる登録免許税 |
|---|---|---|
| 住所変更 | 登記上の住所から現在の住所への移転経緯がわかる公的書類 ※複数回引越しをしている場合は、つながりが証明できる全ての書類が必要です。 | 不動産1個につき1,000円 (土地と建物なら合計2,000円) |
| 氏名変更 | 登記簿上の氏名(変更前の氏名)、現在の氏名、氏名の変更の日が記載されている公的書類が必要です。 |
これらの手続きが必要な場合は、事前に管轄の法務局に相談し、必要書類を正確に確認しておくと安心です。
相続が発生している場合の抵当権抹消登記
不動産の所有者が亡くなられた後に抵当権抹消登記を行う場合は、手続きが複雑になります。状況によっては司法書士への依頼を検討することをおすすめします。
ケース1:ローン完済後に所有者が死亡した場合
この場合、「相続登記」と「抵当権抹消登記」の申請順序は下記の1と2どちらが先でも問題ありません。
1.①「相続登記」を申請して名義を相続人に変更します。その後、新しい名義人となった相続人が申請者(登記権利者)となり、②「抵当権抹消登記」の手続きを進めます。
2.申請者(登記権利者)として亡くなった方の名前を記入し、相続人が代わりに①「抵当権抹消登記」の手続きをし、その後、②「相続登記」を申請して名義を相続人に変更します。
ケース2:所有者が死亡した後にローン完済した場合
所有者が亡くなった後にローン完済した場合は、「相続登記」を行ってから「抵当権抹消登記」を申請します。実務上、相続登記と同時に、抵当権抹消登記を(連件で)申請するのが一般的です。申請順序は必ず①「相続登記」②「抵当権抹消登記」とします。
相続人が複数いる場合や、遺産分割協議がまとまらない場合など、状況は多岐にわたります。ご自身での手続きが難しいと感じたら、無理をせず専門家に相談しましょう。
【関連記事】
「相続登記が義務化されたが相続放棄したらどうなる?期限やリスク・罰則について札幌の司法書士が解説」
書類を紛失してしまった場合の対処法
金融機関から受け取った抵当権抹消登記の必要書類を紛失してしまった場合でも、対処法はあります。慌てずに、どの書類を失くしたかを確認し、適切に対応しましょう。
| 紛失した書類 | 主な対処法 |
|---|---|
| 登記原因証明情報(解除証書など) 金融機関の委任状 | 金融機関に連絡し、再発行を依頼します。 |
| 登記識別情報(または登記済証) | この書類は再発行ができません。そのため、以下の手続きが必要になります。
|
いずれの書類を紛失した場合でも、まずはローンを組んでいた金融機関に連絡することが第一歩です。
法務局での補正(修正)指示への対応方法
登記申請書を提出した後、書類に不備や記載ミスがあると、法務局の担当者から電話で「補正(ほせい)」の連絡が入ることがあります。これは申請が却下されたわけではなく、指定された箇所を修正すれば手続きを進めてもらえるという指示です。
補正は決して珍しいことではありませんので、焦らず冷静に対応しましょう。主な対応方法は以下の通りです。
- 法務局の窓口で修正する:最も確実な方法です。担当者の指示に従い、その場で書類を修正します。修正には申請書に使用した印鑑(訂正印として使います)が必要になるため、必ず持参しましょう。
- 郵送で対応する:軽微な修正の場合、郵送での対応が認められることもあります。その場合は、担当者の指示に従って修正した書類や新しい書類を郵送します。
よくある補正の指示としては、以下のようなものが挙げられます。
- 登録免許税の金額間違いや収入印紙の貼り忘れ
- 申請書の記載と登記簿の内容の不一致(不動産の表示など)
- 添付書類の不足(住所変更を証明する住民票など)
- 印鑑の押し忘れや印影が不鮮明な場合
まとめ
抵当権抹消登記は、司法書士に依頼せず自分で行うことで、数万円の費用を節約できる大きなメリットがあります。手続きは、金融機関から必要書類を受け取り、法務局のウェブサイトで入手できるテンプレートで申請書を作成し、管轄の法務局へ提出するという流れです。住所変更など特殊なケースもありますが、本記事で解説した手順と注意点を参考にすれば、ご自身での登記も十分可能です。住宅ローン完済後は、大切な資産を守るためにも速やかに手続きを完了させましょう。
ルフレ司法書士事務所では、登記手続きに関する様々な業務を扱っております。司法書士が、迅速丁寧にお客様の状況に合わせた最適なサポートを提供いたします。また、司法書士だけでは解決できない案件については、他士業(弁護士さんや税理士さん等)と連携して業務を行っております。
ルフレ司法書士事務所は、全国対応しております。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。