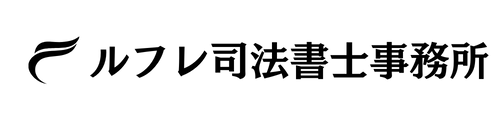見守り契約とは?家族が知っておくべき契約の種類、料金、任意後見契約との関係性について

高齢化社会の進展とともに、離れて暮らす家族の安全を見守りたいというニーズが高まっています。しかし、沢山のサービスがあり、見守り契約とは何か、費用はどれくらいかかるのか、といった具体的な情報を知らない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、見守り契約とは何か、司法書士に依頼した場合の手続きの流れや料金体系まで、ご家族が知っておくべき情報を解説します。この記事が、見守り契約に関する疑問を解消し、お役に立てれば幸いです。
見守り契約とは
高齢化社会の進展に伴い、一人暮らしの高齢者や離れて暮らす家族の安全を見守るニーズがますます高まっています。高齢者の増加に加え、核家族化や地域コミュニティの希薄化といった社会構造の変化も相まって、家族だけでは十分な見守りが難しくなっている現状があります。このような背景から、ご家族以外の第三者による見守りサービスへの需要が拡大し、様々な形態の見守り契約が登場しています。
高齢者の見守りニーズの高まり
高齢者の見守りニーズは多岐に渡ります。例えば、急病や事故時の迅速な対応、日常生活における不安の解消、孤独感の軽減などが挙げられます。具体的には、転倒による骨折や脳卒中などの緊急時の対応、服薬管理や健康状態の確認、日々の安否確認、話し相手が欲しい、といったニーズがあります。これらのニーズに対応するために、様々な見守りサービスが提供されています。
見守り契約の定義と目的
見守り契約とは、利用者(主に高齢者)の安全と安否を確認するためのサービスを提供する契約です。事業者と契約を結び、利用者の状況に応じて、定期的な連絡や緊急時の対応、日常生活の支援などを行います。見守り契約の主な目的は、利用者の安全確保、健康状態の維持、孤独感の軽減、そして家族の安心です。緊急時における迅速な対応や、日々の生活における不安の解消を図ることで、利用者が安心して生活できる環境を整備することを目指します。
見守り契約でできること
見守り契約でできることはサービス提供事業者によって異なりますが、代表的なサービス内容は以下の通りです。
- 緊急通報サービス:利用者が緊急事態に陥った際に、ボタン一つで警備会社や救急へ連絡できる。
- 定期的な安否確認サービス:電話や訪問などにより、定期的に利用者の安否を確認する。
- GPS位置情報サービス:GPS端末を携帯することで、利用者の位置情報を把握できる。
- センサーによる見守りサービス:自宅にセンサーを設置し、利用者の活動状況をモニタリングする。例えば、トイレや浴室の使用状況、部屋の温度変化などを検知し、異常があれば家族や事業者に通知する。
- 訪問型見守りサービス:事業者のスタッフが定期的に自宅を訪問し、安否確認や生活支援を行う。例えば、掃除、洗濯、買い物、調理などの家事援助や、服薬管理、通院介助なども行う場合がある。
見守り契約とその他の契約との関係(任意後見契約、財産管理契約など)
ここからは、司法書士による見守りサービスの契約、契約の流れ、料金体系についてご説明します。
まず、司法書士に依頼する場合の、他の契約との関係性についてですが、任意後見制度を利用する場合、見守り契約や財産管理契約は、オプション的な位置付けになることが一般的です。
任意後見契約は、将来、ご自身の判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ後見人となってくれる人と契約を締結します。任意後見人の仕事は、ご本人の判断能力が低下した時に始まりますが、そのご本人が一人暮らしで、定期的に連絡を取っているご家族もいない場合、ご本人の変化に気づくことができません。そういった場合に利用されるのが、見守り契約です。
司法書士が任意後見を受任する場合は、見守り契約が必要かどうか確認します。見守り契約をご希望の場合は、司法書士が定期的にご本人と連絡を取ることによって、判断能力の状況を確認します。また、判断能力が低下する前のご本人の財産管理もご希望であれば、財産管理契約も締結して、ご本人の代わりに司法書士が財産管理を行います。
【ご本人の判断能力が低下する前】
任意後見契約・・・ご自身の判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ後見人となってくれる人と契約する
見守り契約・・・判断能力が低下する前の、定期的なご本人の状況確認が必要な場合
財産管理契約・・・判断能力が低下する前の、ご本人の財産管理が必要な場合(例 預貯金の管理等)
【ご本人の判断能力が低下した後】
任意後見契約・・・任意後見人の職務が開始し、ご本人の財産管理や身上監護を行う
【ご本人が亡くなった後】
死後事務委任契約・・ご本人が亡くなった後の事務手続きを委任する契約(例 葬儀の手配、死亡届の提出等)
遺言執行者・・遺言書に記載された相続手続きを行う(例 不動産の名義変更、遺贈の手続き等)
このように、それぞれの契約は目的や内容が異なるため、利用者の状況やニーズに合わせて適切な契約を選択することが重要です。
【関連記事】
「任意後見制度とは?家族が知っておくべき基本情報」
見守り契約の流れ
司法書士と見守り契約をした場合の、手続きの流れは下記のようになります。
1 見守り契約の内容を決める(電話や訪問する頻度や時間、その他のご要望事項)
⇩
2 公正証書を作成する(任意後見契約に見守り契約の内容を盛り込むことで費用が節約できます)
見守り契約の料金体系
司法書士による見守り契約の費用は、下記のようになります。
初期費用(公正証書作成費用)
初期費用として、見守り契約書を公正証書で作成する費用がかかります。司法書士報酬の相場が2~3万円、公証人手数料が1万1000円で、合計3万1000円~になります。
月額料金
月額料金の相場は、月1回の訪問と電話で1万円~(別途、交通費等の実費が発生)です。電話や訪問する頻度や時間が多くなれば、その分費用も高くなります。
まとめ
高齢化が進む現代社会において、離れて暮らすご家族の安全を見守ることは重要な課題です。この記事では、見守り契約について、その定義から料金体系までを解説しました。
ルフレ司法書士事務所では、生前対策や認知症対策に関する様々な業務を扱っております。司法書士が、迅速丁寧にお客様の状況に合わせた最適なサポートを提供いたします。また、ご希望に応じて他士業(弁護士さんや税理士さん)を紹介しております。
全国対応していますので、お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。