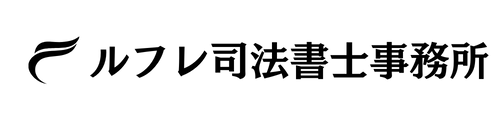2025年10月開始!公正証書のデジタル化・電子化を徹底解説|リモート作成や新手数料も

2025年10月、公正証書はデジタル化により大きく変わります。本記事では、インターネット経由での嘱託やウェブ会議(リモート)での作成、電子サインの導入といった変更点の全貌を徹底解説。リモート作成の具体的な手順、対面手続きの変更点、改定後の新手数料まで網羅的に分かります。公証役場へ行かずに手続きが完結できるようになるなど、利便性が向上する公正証書の電子化について、気になる疑問もQ&Aで解消します。
公正証書のデジタル化とは?2025年からの3つの主要な変更点
2025年10月1日から改正公証人法が施行され、公正証書の作成手続きが大きく変わります。これまで紙媒体が基本だった公正証書が、原則として電子データで作成・保存される「デジタル化(電子化)」がスタートします。これにより、手続きの利便性が大幅に向上することが期待されています。
ただし、このデジタル化対応はすべての公証役場で一斉に開始されるわけではなく、国が指定した「指定公証人」が在籍する公証役場から順次導入される予定です。ここでは、公正証書のデジタル化によって何がどう変わるのか、主要な3つの変更点を詳しく解説します。
| 項目 | これまでの手続き(〜2025年9月) | 新しい手続き(2025年10月〜) |
|---|---|---|
| 嘱託(作成の依頼) | 公証役場へ来所し、書面で手続き | インターネット経由での嘱託が可能に |
| 作成方法 | 公証人と対面で作成 | ウェブ会議(リモート)での作成が可能に |
| 原本の形式 | 紙の文書 | 電子データ(PDF)が原則に |
| 署名・押印 | 自署と実印の押印 | 電子サインと電子署名を導入(押印不要) |
【参考情報】
日本公証人連合会:令和7年秋、公正証書の電子化がスタート!対面方式による電子公正証書の作成のポイントを解説(YouTube)
日本公証人連合会:令和7年秋、公正証書の電子化がスタート!リモート方式による電子公正証書の作成手順(YouTube)
インターネット経由での嘱託が可能に
これまで公正証書の作成を依頼する「嘱託(しょくたく)」は、原則として公証役場へ出向き、印鑑証明書などの書類を提出して本人確認を行う必要がありました。
2025年10月からは、この嘱託手続きがオンラインで完結できるようになります。マイナンバーカードなどに搭載されている電子証明書と電子署名を付した嘱託情報を、メールなどを利用してインターネット経由で送信することにより、公証役場へ行かなくても手続きを進めることが可能になります。これにより、遠隔地にお住まいの方や、多忙で時間を確保するのが難しい方でも、より手軽に公正証書の作成を依頼できるようになります。
ウェブ会議(リモート)での作成が実現
公正証書の作成は、公証人が嘱託人(依頼者)と直接対面し、本人の意思や内容を確認することが法律で定められています。そのため、従来は必ず公証役場に出向くか、公証人に出張してもらう必要がありました。
今回のデジタル化により、嘱託人の希望があり、公証人が相当と認める場合に限り、ウェブ会議システム(Microsoft Teamsなどを利用)を通じたリモート方式での作成が認められます。パソコンの画面越しに公証人とやり取りをしながら、内容の読み合わせや本人確認を行うことで、自宅や職場にいながら公正証書を完成させることが可能になります。地理的な制約や身体的な事情で公証役場への訪問が困難だった方にとって、大きなメリットとなる変更点です。
原本が電子データになり電子サインを導入
今回の改正で最も大きな変更点が、公正証書の原本そのものの電子化です。
これまでは紙の文書として作成され、署名・押印のうえ公証役場で厳重に保管されていました。2025年10月以降は、原則としてPDF形式の電子データが「原本」となります。この電子原本には、改ざん防止のための高度な技術が用いられます。
これに伴い、署名・押印の方式も変わります。
- 嘱託人・証人など:紙への署名・押印に代わり、タッチパネル機能付きのディスプレイやペンタブレットを使い、電子ペンで手書きする「電子サイン」を行います。これにより押印は不要となります。
- 公証人:嘱託人同様の「電子サイン」に加え、公証人の身分と権限を証明する「電子署名」を付与します。この電子署名によって、その電子データが正当な公証人によって作成された真正な公正証書であることが担保されます。
完成した公正証書の正本や謄本は、従来の紙の書面での受け取りに加えて、電子データ(電子正本・電子謄本)で受け取ることも可能になります。電子データは、指定されたクラウドサーバーからダウンロードしたり、持参したUSBメモリに保存してもらったりする方法で交付されます。
【リモート編】ウェブ会議で公正証書を作成する全手順
2025年10月から、公証役場に出向かなくても、自宅やオフィスのパソコンから公正証書を作成できる「リモート方式」が導入されます。ここでは、ウェブ会議を利用した新しい公正証書作成のメリット、必要な準備、そして当日の具体的な流れを詳しく解説します。
リモート作成のメリットと利用できる条件
リモート方式の導入により、公正証書の作成がより手軽で便利になります。まずは、そのメリットと利用するための条件を確認しましょう。
リモート作成の主なメリット
- 場所を選ばない
インターネット環境があれば、自宅やオフィスなど、どこからでも手続きが可能です。公証役場への移動時間や交通費を節約できます。 - 遠隔地の当事者とも作成可能
相続人や契約の相手方が遠方に住んでいる場合でも、同じ日時にウェブ会議に参加することで、スムーズに公正証書を作成できます。 - 柔軟な対応
病気や怪我、育児や介護などで外出が難しい方でも、公正証書を作成しやすくなります。 - 非対面での手続き
離婚給付契約など、相手方と直接顔を合わせたくない事情がある場合にも有効です。また、感染症予防の観点からも安心して手続きを進められます。
リモート作成を利用できる条件
リモート作成は、誰でも無条件に利用できるわけではありません。以下の条件を満たす必要があります。
- 嘱託人(または代理人)からの申出があること
リモート方式を利用したい旨を、事前に公証役場に申し出る必要があります。 - 他の嘱託人に異議がないこと
契約の相手方など、他の嘱託人の異議がある場合は、利用できません。 - 公証人がリモートでの作成を「相当」と認めること
公証人が、ウェブ会議を通じて嘱託人の本人確認や意思確認、判断能力の確認が問題なく行えると判断した場合にのみ利用が認められます。嘱託内容や当事者の状況によっては、対面での手続きを求められることもあります。 - 法律上リモート作成が認められている公正証書であること
例えば、保証人の意思を確認する「保証意思宣明公正証書」など、一部の公正証書はリモート作成の対象外となります。
事前に準備が必要なもの(PC・機材・環境)
リモート方式で公正証書を作成するには、特定の機材と環境が必要です。公証役場から指定されたものを事前に準備しましょう。スマートフォンやタブレットは、画面共有や電子サインの機能要件を満たさないため利用できません。
| 分類 | 必要なもの | 詳細・注意点 |
|---|---|---|
| パソコン | OS・ブラウザ | Windows 10/11またはmacOS。ブラウザは最新版のMicrosoft Edge, Google Chrome, Firefox, Safariなどが推奨されます。 |
| 周辺機器 | ウェブカメラ・マイク | PCに内蔵されているもので構いません。本人確認や意思疎通のために必須です。 |
| 電子サイン用機器 | タッチ入力対応ディスプレイと電子ペン、またはペンタブレットと電子ペンのいずれかが必要です。 | |
| 通信環境 | インターネット回線 | 映像と音声が途切れない、安定したブロードバンド接続が推奨されます。 |
| メールアドレス | ウェブ会議の招待メールや電子サインの依頼メールを受信するために、利用するPCで確認できるメールアドレスが必要です。 | |
| 場所 | 静かな個室 | 手続きの内容が第三者に漏れないよう、プライバシーが確保された静かな環境を準備してください。 |
当日の流れを5ステップで解説
事前の打ち合わせで公正証書の案文が完成したら、いよいよウェブ会議による作成当日を迎えます。当日の手続きは、概ね以下の5つのステップで進行します。
ステップ1:ウェブ会議への参加と本人確認
まず、公証人から事前にメールで送られてきたURLをクリックし、指定されたウェブ会議システム(Microsoft Teamsなど)に入室します。会議が始まったら、公証人の指示に従い、カメラとマイクが正常に作動するかを確認します。その後、運転免許証やマイナンバーカードなどの写真付き身分証明書をカメラに提示し、公証人が画面キャプチャ等で本人確認を行います。
ステップ2:画面共有による公正証書案の読み上げ・確認
本人確認が完了すると、公証人がパソコンの画面を共有し、最終版の公正証書案を表示します。公証人が案文を読み上げますので、当事者は画面を見ながら内容に間違いがないか、最終的な意思確認を行います。ここで全員が内容に同意すれば、公証人は原本となる電子データ(PDF形式)を作成します。
ステップ3:電子サインの実施
公正証書の電子データに、当事者が署名(電子サイン)を行います。この手続きは、公証人が操作を確認する必要があるため、ご自身のパソコン画面を共有しながら進めます。
- 公証人から電子サインを依頼するメールが届きます。
- メール内のリンクをクリックして、署名画面を開きます。
- ウェブ会議システムに戻り、「画面共有」機能を使ってご自身のパソコン画面全体を公証人に見せます。
- 準備した電子ペンやペンタブレットを使い、署名欄にサインをします。
- サイン後、「適用」「送信」などのボタンをクリックして署名を確定させます。
- 署名が完了したら、画面共有を停止します。
複数の当事者がいる場合は、一人ずつ順番にこの作業を繰り返します。
ステップ4:公証人による電子署名と原本の完成
すべての当事者の電子サインが完了すると、最後に公証人が電子サインと「電子署名」を行います。この公証人による電子署名は、その公正証書が間違いなく公証人によって作成されたことを証明するもので、これをもって法的に有効な電子公正証書の「原本」が完成します。完成した電子原本は、改ざんを検知できる仕組みになっています。
ステップ5:電子正本・謄本の受け取り方法
手続きが完了すると、公証人は完成した電子原本から「電子正本」や「電子謄本」を作成します。受け取り方法は以下の通りです。
- 公証人が電子正本・謄本のデータを、セキュリティで保護されたクラウドストレージにアップロードします。
- 当事者には、データをダウンロードするためのURLが記載されたメールが届きます。
- ダウンロードに必要なパスワードは、安全のため、ウェブ会議のチャット機能などメールとは別の方法で公証人から通知されます。
- メールのURLにアクセスし、パスワードを入力してデータをダウンロードします。
- ダウンロードが完了したことを公証人に報告し、すべての手続きが終了となります。
このように、リモート方式を利用すれば、準備さえ整えればスムーズかつ安全に公正証書を作成することが可能です。
【対面編】公証役場での手続きはどう変わる?
2025年10月1日から、公正証書の作成手続きはデジタル化が基本となります。これはウェブ会議(リモート)での作成に限った話ではありません。これまで通り公証役場に直接出向いて手続きを行う「対面方式」においても、そのプロセスが大きく変わります。ここでは、公証役場を訪れて公正証書を作成する場合の変更点を詳しく解説します。
来所する場合でも原本は電子データに
対面手続きにおける最も大きな変更点は、公正証書の「原本」が、従来の紙の書類から電子データ(PDF形式)になることです。これにより、手続きの根幹がデジタルベースに移行します。
これまで嘱託人(依頼者)や証人が行っていた紙への署名・押印は不要となり、後述する「電子サイン」に置き換わります。完成した電子公正証書の原本は、公証役場のシステムで厳格に管理・保存されます。
この変更点を、従来の手続きと比較してみましょう。
| 項目 | 従来の手続き(~2025年9月) | 新制度での対面手続き(2025年10月~) |
|---|---|---|
| 原本の形式 | 紙の書面 | 電子データ(PDF形式) |
| 嘱託人・証人の意思表示 | 書面への署名・押印 | ディスプレイへの電子サイン(押印不要) |
| 公証人の認証 | 書面への署名・押印 | 電子サインおよび電子署名 |
| 原本の保管 | 公証役場にて紙で保管 | 公証役場のシステムにて電子データで保管 |
ただし、すべてのケースで電子化が強制されるわけではありません。例えば、「保証意思宣明公正証書」のように法律上、紙での作成が求められるものや、添付資料が膨大で電子化(PDF化)が著しく困難な場合など、やむを得ない事情がある場合は、例外的に従来通り紙の公正証書を作成することも可能です。
対面での電子サインの方法
公証役場での手続きがデジタル化されると聞くと、特別な機材の準備が必要かと不安に思うかもしれませんが、その心配は不要です。対面方式の場合、電子サインに必要なパソコン、タッチ機能付きディスプレイ、電子ペンといった機材はすべて公証役場側で用意されます。嘱託人(依頼者)が持参する必要があるのは、従来通り本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)や実印、印鑑証明書(必要な場合)といった書類のみです。
当日の手続きは、以下の流れで進められます。
ステップ1:本人確認と公正証書案の最終確認
まず、公証人が持参した本人確認書類で本人確認を行います。その後、事前に打ち合わせを重ねて作成した公正証書の最終案を、ディスプレイ画面上または紙に印刷したもので確認します。公証人が内容を読み上げ、嘱託人や証人などがその内容に間違いがないか、最終的な意思確認を行います。このステップは、従来の手続きと大きくは変わりません。
ステップ2:電子サインの実施
公正証書の内容が確定したら、いよいよ電子サインを行います。公証人が最終案から原本となるPDFファイルを作成し、電子サイン用のPCを嘱託人の前に設置します。嘱託人は、画面に表示された署名欄に、備え付けの電子ペンを使って自身の氏名を手書きで入力します。この際、焦らずゆっくりと書くことで、滑らかなサインが記録できます。署名が終わったら、画面の指示に従って「適用」「送信」といったボタンを操作し、サインを確定させます。証人など、他に署名する人がいる場合は、一人ずつ順番に同じ操作を繰り返します。
ステップ3:公証人による電子署名と原本の完成
嘱託人や証人など、すべての関係者の電子サインが完了すると、最後に公証人が自身の電子サインと、法的な効力を持つ「電子署名」をPDFファイルに付与します。この公証人の電子署名が行われた時点で、改ざん防止機能が施された法的に有効な「電子公正証書」の原本が完成します。
ステップ4:電子正本・謄本の受け取り
完成した公正証書の「正本」や「謄本」(いずれも原本の写し)の受け取り方法を選択できます。受け取り方法は主に以下の2つです。
- 書面での受け取り:電子公正証書のデータを印刷したものを、これまで通り紙の正本・謄本として受け取ります。
- 電子データでの受け取り:電子正本・電子謄本のデータを、CD-Rや持参したUSBメモリなどの記録媒体に保存してもらい、データとして受け取ります。
提出先が電子データでの提出を認めている場合など、用途に応じて便利な受け取り方法を選ぶことができます。
2025年10月からの新手数料を解説
2025年10月1日から施行される公証人法の改正に伴い、公正証書の作成手続きがデジタル化されるのと同時に、各種手数料も見直されます。この改定は、デジタル化への対応だけでなく、近年の物価上昇や社会情勢の変化を反映し、利用者の負担を適正化することを目的としています。ここでは、新しい手数料体系のポイントと具体的な金額を詳しく解説します。
手数料改定のポイント
今回の手数料改定には、大きく分けて3つのポイントがあります。
1. デジタル化に伴う手数料の新設
公正証書の原本が電子データになることに伴い、電子化された正本・謄本を提供するための手数料が新たに設けられます。紙での交付も引き続き可能ですが、手数料体系が異なります。
- 電子データでの提供(電子正本・謄本): 1通 2,500円
- 紙の書面での交付(紙の正本・謄本): 用紙1枚当たり 300円
2. 社会的ニーズへの対応と負担軽減
ひとり親家庭や身寄りのない高齢者など、特定のニーズが高い契約について、手数料の負担が軽減されるよう見直しが行われました。
- 養育費に関する契約: これまで手数料算定の基礎となる給付価額は最大10年分でしたが、改定後は最大5年分に短縮されます。これにより、養育費に関する公正証書の作成手数料が引き下げられます。
- 死後事務委任契約: 高齢化社会のニーズに応え、通常の委任契約の手数料の半額に減額されます。
3. 物価上昇など経済情勢への対応
近年の物価上昇などを考慮し、基本的な手数料体系が全体的に見直され、一部の手数料が改定されています。
目的別の新しい手数料一覧
具体的な手数料は、公正証書の種類や目的の価額によって異なります。ここでは主要な手数料を一覧でご紹介します。
法律行為に関する公正証書
売買契約、金銭消費貸借契約、遺言、任意後見契約など、法律行為に関する公正証書の作成手数料は、目的の価額に応じて以下の通り定められています。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 50万円まで | 3,000円 |
| 100万円まで | 5,000円 |
| 200万円まで | 7,000円 |
| 500万円まで | 13,000円 |
| 1,000万円まで | 20,000円 |
| 3,000万円まで | 26,000円 |
| 5,000万円まで | 33,000円 |
| 1億円まで | 49,000円 |
| 3億円まで | 49,000円に超過額5,000万円までごとに15,000円を加算 |
| 10億円まで | 109,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算 |
| 10億円を超える場合 | 291,000円に超過額5,000万円までごとに9,000円を加算 |
【手数料算定の主な注意点】
- 法律行為の目的の価額を算定できないときは、500万円とみなされ、手数料は13,000円となります。
- 定期給付(養育費、賃貸借など)を目的とする場合、原則として全期間の給付総額が目的の価額となります。ただし、子の養育費、動産の賃貸借、雇用の契約については5年分、その他の法律行為では10年分が上限となります。
- 死後事務委任契約については、上記の手数料表で算定された額の半額となります。
- 遺言公正証書や信託契約公正証書については、目的の価額が1億円以下の場合、上記手数料に13,000円が加算されます。
- 公正証書の枚数が法務省令で定める枚数を超える場合は、超過枚数に応じて手数料が加算されます。
法律行為でない事実に関する公正証書
尊厳死宣言公正証書や、事実を実験してその結果を記述する事実実験公正証書などがこれにあたります。事実実験公正証書の手数料は、実験や記録に要した時間に応じて計算されます。
- 事実の実験およびその録取: 1時間までごとに13,000円
認証手数料
私署証書(個人や法人が作成した文書)の認証手数料については、基本的な枠組みは変わりません。ただし、私署証書の認証手数料は「その文書を公正証書として作成した場合の手数料の半額」が基準となるため、今回の公正証書手数料の改定に伴い、結果的に金額が変わる場合があります。具体的な金額については、認証を依頼する公証役場にご確認ください。
公正証書デジタル化に関するよくある質問(Q&A)
2025年10月から始まる公正証書のデジタル化・電子化。多くのメリットがある一方で、「手続きはどう変わるの?」「安全性は大丈夫?」といった疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。ここでは、公正証書のデジタル化に関してよく寄せられる質問とその回答を、Q&A形式でわかりやすく解説します。
Q. すべての公証役場でデジタル対応していますか?
A. いいえ、2025年10月1日から一斉に全国の公証役場で対応が始まるわけではありません。法務大臣によって指定された「指定公証人」が在籍する公証役場から、順次デジタル手続きが利用可能になります。
そのため、ウェブ会議(リモート)での作成など、デジタル化された手続きを利用したい場合は、事前に依頼を検討している公証役場が対応しているかどうかを電話や公式ウェブサイトで確認する必要があります。対応する公証役場は、今後、日本公証人連合会のウェブサイトなどで公表される予定です。
Q. スマートフォンやタブレットは使えますか?
A. いいえ、ウェブ会議(リモート)方式で公正証書を作成する場合、スマートフォンやタブレットは使用できません。パソコン(WindowsまたはmacOS)が必須となります。
理由としては、公正証書案の内容を正確に確認するための「画面共有機能」や、手続きに不可欠な「電子サイン」を安定した環境で行う必要があるためです。具体的には、以下の機材・環境をご自身で準備する必要があります。
- ウェブ会議が可能なパソコン(Windows 10/11 または macOS)
- ウェブカメラ、マイク、スピーカー(パソコン内蔵のもので可)
- 電子サインを行うための機器(タッチ入力対応ディスプレイ、またはペンタブレットと電子ペン)
- ウェブ会議の招待メールなどを受信できるメールアドレス
Q. 紙の公正証書はもう作成できなくなりますか?
A. いいえ、紙の公正証書が完全になくなるわけではありません。ご安心ください。デジタル化後の扱いは、大きく分けて2つのケースがあります。
- 原則は「電子データ」が原本になる
2025年10月以降、公正証書の原本は原則として電子データ(PDF形式)で作成・保存されます。そして、その電子原本の写しとして「電子正本・謄本」または「書面正本・謄本(紙)」のどちらか、あるいは両方を受け取ることができます。つまり、手元に紙の証明書が欲しい場合は、これまで通り紙で受け取ることが可能です。 - 例外的に「紙」で原本を作成する場合もある
「保証意思宣明公正証書」のように、法律上、書面での作成や署名押印が必須とされている特定の公正証書については、引き続き紙で原本が作成されます。また、添付資料が大量で電子化(PDF化)が困難な場合など、やむを得ない事情がある場合も、例外的に紙での作成が認められることがあります。
Q. 電子化された公正証書の安全性・法的効力は?
A. 電子化された公正証書の法的効力は、従来の紙の公正証書と全く同じです。また、安全性については、むしろ紙よりも高いレベルで確保されています。
法的効力について
今回のデジタル化は、公証人法という法律に基づいて行われる正式な手続きです。電子データで作成された公正証書も、法律上の要件をすべて満たしており、遺言の効力や契約の強制執行力など、その法的な力に何ら変わりはありません。
安全性(改ざん防止)について
電子公正証書の原本には、公証人が国の厳格な認証制度に基づいた「電子署名」を付与します。この電子署名には、いつ、誰が作成したかを証明し、その後にデータが改ざんされていないことを検知する仕組みが組み込まれています。万が一、データが不正に変更された場合、その記録が残るため、偽造や改ざんを極めて困難にします。これにより、紙の文書以上に高い真正性が担保されると言えます。
Q. デジタル化で作成できない公正証書はありますか?
A. はい、一部あります。原則として多くの公正証書がデジタル化の対象となりますが、法律の規定により、ウェブ会議(リモート)方式での作成が認められていないものや、引き続き紙での作成が必要なものがあります。
代表的な例は、事業用の融資などで保証人になる際に作成する「保証意思宣明公正証書」です。この公正証書は、保証人になろうとする本人が公証人の面前で直接意思を述べることが法律で厳格に定められているため、リモートでの作成はできず、公証役場へ出向いて手続きを行う必要があります。
Q. 電子データと紙、どちらで受け取るべきですか?
A. 電子データ(電子正本・謄本)と紙(書面正本・謄本)のどちらで受け取るかは、その公正証書をどのように利用するかによって選択するのがよいでしょう。それぞれの特徴と手数料を以下の表にまとめました。
| 交付形態 | 受け取り方法 | 2025年10月からの新手数料 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 電子正本・謄本 (電子データ) |
| 1通につき 2500円 |
|
|
| 書面正本・謄本 (紙) | 公証役場で直接交付 | 用紙1枚につき 300円 |
|
|
※上記手数料は、公正証書作成の基本手数料とは別に必要となる交付手数料です。
例えば、金融機関への提出や不動産登記など、提出先がまだ電子データに対応していない場合も考えられるため、事前に提出先に必要な形式を確認しておくことをお勧めします。もちろん、電子データと紙の両方を受け取ることも可能です。
まとめ
2025年10月から、公正証書の作成手続きがデジタル化によって大きく変わります。最大の変更点は、ウェブ会議を利用して公証役場へ行かずにリモートで作成が可能になることです。また、原本が電子データとなり、従来の署名押印に代わって電子サインが導入されます。これにより、遠方にお住まいの方や多忙な方でも、より手軽に公正証書を作成できるようになります。手数料も改定されるため、新しい制度の内容を正しく理解し、遺言や契約に備えましょう。
ルフレ司法書士事務所では、相続手続きや生前対策に関する様々な業務を扱っております。司法書士が、迅速丁寧にお客様の状況に合わせた最適なサポートを提供いたします。また、司法書士だけでは解決できない案件については、他士業(弁護士さんや税理士さん等)と連携して業務を行っております。
ルフレ司法書士事務所は、全国対応しております。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。