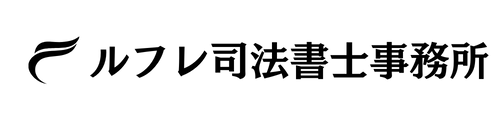清算人の選任の登記の費用と手続きを分かりやすく解説|司法書士監修で安心!

会社を解散する際に必要な「清算人」の選任登記。この記事では、清算人の役割、具体的な登記手続きの流れ、費用相場、そして登記の際の注意点まで、司法書士の監修のもと分かりやすく解説します。この記事を読むことで、清算人選任登記に必要な書類、法務局への申請方法、登録免許税や司法書士への依頼する場合の費用、知りたい情報が全て網羅的に分かります。清算人の選任登記に関する疑問を解消し、安心して手続きを進められるよう、ぜひ最後までお読みください。
清算人とは
清算人とは、会社や一般社団法人などの法人が解散した場合に、残っている業務があれば完成させ、債権の回収や債権者への弁済、残余財産の株主への分配などを行うために選任される人のことです。会社の清算事務(=後始末)を任された人のことを指します。清算人は、清算結了登記をして法人格が消滅するまでの間、清算事務に必要な行為を行うことができます。
清算人の役割
清算人の主な役割は、解散した法人の財産を整理し、債権者への弁済を行うことです。具体的には、以下の業務を行います。
- 現存する業務の終了
- 債権の取立て
- 債務の弁済
- 残余財産の株主への分配
- 株主への清算事務に関する報告
- 登記手続き(清算結了の登記など)
これらの業務を適切に行うことで、解散した法人の事務を円滑に終了させることが清算人の重要な役割となります。
清算人と破産管財人の違い
清算人と破産管財人は、どちらも法人の財産を整理するという点で共通していますが、その役割や選任される場面は大きく異なります。主な違いは以下の通りです。
| 項目 | 清算人 | 破産管財人 |
|---|---|---|
| 選任される場面 | 会社が自主的に解散する場合 | 会社が破産手続き開始決定を受けた場合 |
| 役割 | 残余財産の整理、債権者への弁済、清算事務に関する報告など | 破産財団の管理・処分、債権者への配当など |
| 選任方法 | ①定款 ②株主総会決議 ③取締役 ④裁判所 | 裁判所による選任 |
| 監督 | 株主 | 裁判所 |
このように、清算人は自主的な解散に伴う財産の整理を行うのに対し、破産管財人は裁判所の監督の下で破産手続きを進めるという違いがあります。清算人は債権者への弁済を優先しますが、破産管財人は債権者の平等を図ることを重視します。会社が債務超過の場合でも、破産手続きをしないで清算する方法(任意整理)もありますが、裁判所の破産手続き開始決定を受けると、破産管財人が選任され、会社の財産は破産財団として管理・処分されることになります。
清算人の選任の流れ
株主総会の決議により解散することになった場合は、清算人の選任の流れは、以下のようになることが一般的です。
株主総会による解散および清算人の選任の決議
⇩
登記申請(解散および清算人の選任の登記)
⇩
債権者保護手続き(官報公告・知れてる債権者への個別催告)
⇩
清算手続き(債権者への弁済、残余財産の株主への分配など)
⇩
決算報告(株主総会への決算報告)
⇩
登記申請(清算結了の登記)
清算人の選任も含めた会社の解散については、こちらの記事をご覧ください。「もう迷わない!会社の解散をスムーズに進めるための登記手続きとポイント」
清算人の選任方法
清算人の選任については、株主総会で清算人を選任する以外にもいくつか方法があります。
定款で定める
清算人及び代表清算人の名前を定款に定める方法や、選任方法について定める方法もあります。
株主総会決議によって選任する
株主総会で解散決議をした際に、清算人および代表清算人を併せて選任することも、実務では一般的です。
代表取締役が代表清算人、取締役が清算人になる
定款の定めもなく、株主総会でも決まらない場合、代表取締役が代表清算人として、取締役が清算人に就任することになります。これらは法定清算人といいます。
裁判所による選任
上記のいずれの方法によっても、清算人となる人がいない場合、株主等の利害関係人による申立により、裁判所が選任します。
清算人の登記手続き
清算人が決まったら、法務局へ登記申請を行う必要があります。ここでは、清算人選任の登記申請に必要な書類と、登記申請の流れについて詳しく解説します。
清算人選任の登記申請に必要な書類
清算人選任の登記申請には、以下の書類が必要です。
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 登記申請書 | 法務局へ提出する申請書で、フォーマットは法務局のホームページからダウンロードできます |
| 定款 | 清算人会設置会社の定めの有無を確認するため |
| 株主総会議事録 | 株主総会決議で清算人を選任した場合に必要 |
| 株主リスト | 株主総会決議で清算人を選任した場合に必要 |
| 就任承諾書 | |
| 委任状 | 司法書士に登記手続きを委任する場合 |
申請方法
作成した申請書と必要書類を、会社の本店所在地を管轄する法務局に提出します。申請は、登記・供託オンライン申請システムを使用してオンラインで申請するか、紙の申請書を会社の所在地を管轄する法務局に提出します。紙の申請書の場合、郵送(実務上レターパックを使用することが多いです。添付書面の原本還付を希望する場合、その分のレターパックも同封します)での申請も可能ですが、窓口で直接申請することもできます。電子申請の場合は、マイナンバーカードに格納されている電子証明書等が必要になります。
各申請方法にはメリット・デメリットがありますので、会社の状況に合わせて最適な方法を選択しましょう。登記手続きに慣れている場合は、オンラインで電子申請して、必要に応じて添付書面のみを郵送で送るのが楽だと思いますが、初めて手続きをする方は、紙で申請書を作成して、窓口に提出するか、郵送で送った方が難易度は低いです。
それぞれの手順やメリット・デメリットを詳しく解説します。
申請書による申請
従来から行われている紙の申請書による申請方法です。必要書類を揃えて、管轄の法務局へ直接持参するか、郵送で提出します。
申請の手順
- 必要書類を作成および収集し、印刷する
- 登録免許税を収入印紙で納付する(収入印紙貼付台紙に収入印紙を貼ります)
- 法務局へ持参または郵送で提出する
- 登記完了
紙による申請のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| インターネット環境が不要 | 法務局へ行く必要がある、または郵送の手間がかかる |
| はじめて登記申請をする人にはオンラインよりも難易度が低め | 書類の不備があった場合、補正で法務局まで出向く必要がある。 |
電子申請
インターネットを利用して、登記・供託オンライン申請システムで申請を行う方法です。法務局へ行く必要がなく、月曜日から金曜日までの8時30分から21時まで(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)いつでも手続きが可能です。電子署名が必要となります。
電子申請の手順
- 電子証明書の取得(マイナンバーカードを使う場合は取得不要)
- 申請書類の作成(登記・供託オンライン申請システムで作成する)
- 電子申請
- 添付書面を郵送で法務局に送る
- 登録免許税のオンライン納付又は収入印紙貼付台紙に収入印紙を貼って添付書面と一緒に郵便で送る
- 登記完了
電子申請に必要なもの
- パソコン
- インターネット環境
- 電子証明書
- PDF作成ソフト
- ICカードリーダー
電子申請のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 平日8時30分から21時までの時間いつでも申請可能 | インターネット環境と電子証明書が必要 |
| 法務局へ行く必要がない | 電子申請システムの操作に慣れが必要 |
申請方法の選択
時間や手間をなるべく省きたい場合は電子申請、手続きに慣れていない又はインターネット環境がない場合は紙の申請書による申請がおすすめです。
申請先
商号変更登記の申請は「会社の本店所在地を管轄する法務局」に対して行います。管轄法務局を調べるには、法務局のホームページを参照するか、「会社 登記管轄 ○○」のように、本店所在地を入れてインターネットで検索すると良いと思います。不動産登記と会社の登記では管轄が違う場合があります。申請先を間違えると、申請が却下されますので、注意が必要です。
登記完了
不動産登記と違い、法務局の手続きが完了しても登記を完了したことを証明する登記完了証や登記識別情報のような権利証は発行されません。
変更後の登記内容を確認したい場合は、別途、登記簿謄本(登記事項証明書)を窓口又は登記・供託オンライン申請システムで請求するか、登記情報提供サービスで確認します。費用は登記簿謄本の場合、480円(郵送で送ってもらう場合は500円)、登記情報サービスで閲覧する場合、331円です。
登記完了までの期間は、法務局の混雑状況にもよりますが、通常1週間から2週間程度です。通常より早く完了する場合もあります。
清算人の登記費用
清算人を選任した場合、法務局への登記が必要となります。この登記には費用が発生します。費用の内訳を把握しておきましょう。
登録免許税
清算人の選任登記にかかる登録免許税は、9000円です。これは株式会社、合同会社等の持分会社、一般社団法人、一般財団法人など一律の金額です。
また、解散の登記を一緒に行う際は、登録免許税3万円が必要となります。最終的に清算結了の登記をする際に登録免許税2000円もかかります。会社の機関設計によって、それ以外にかかる場合もありますので、全体にかかる費用を事前に把握しておくことをお勧めします。
司法書士に依頼した場合の費用相場
清算人の選任登記は、自分自身で行うこともできますが、解散手続きは複雑なため、解散に関係する登記全て(解散・清算人の選任・清算結了)を、まとめて司法書士に依頼することが一般的です。解散に関係する登記全て(解散・清算人の選任・清算結了)を司法書士に依頼した場合の報酬相場は8万円~です。登録免許税や司法書士報酬の他に、官報公告の費用や、郵送費がかかります。
司法書士への報酬は、事案の難易度や作業量によっても変動します。登録免許税も会社の機関設計によって変わりますので、事前に司法書士に費用の見積もりを依頼し、内容を確認しておくことが大切です。
| 費用項目 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 最低4万1000円(監査役設置会社の場合は、8万1000円or10万1000円) ※株式会社・合同会社で金額に違いはありません。 | 内訳:解散(3万円)、清算人の選任(9000円)、清算結了(2000円)、監査役の退任(1万円or3万円)、監査役設置会社の定め廃止(3万円) |
| 官報公告料 | 4万円前後 | 詳しくはこちらをご覧ください。 |
| 司法書士報酬 | 司法書士報酬:8万円~ | 手続きの依頼内容によって変動します。 |
| 郵送費、交通費等 | 数千円~ | 必要に応じて発生します。 |
まとめ
この記事では、清算人の選任登記の手続き、費用、注意点について解説しました。清算人は、会社や一般社団法人・一般財団法人が解散する際に、残余財産の分配や債務の弁済などを行う重要な役割を担います。清算人選任登記は、解散手続きにおける重要なステップです。この記事が参考になれば幸いです。
ルフレ司法書士事務所では、設立登記をはじめ、役員変更など、会社の登記に関する様々な業務を扱っております。司法書士が、迅速丁寧にお客様の状況に合わせた最適なサポートを提供いたします。
全国対応してますので、会社の手続きでお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。