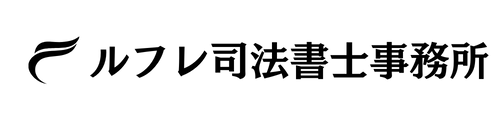【2026年4月施行】住所変更登記の義務化とは?かんたん・無料の「スマート変更登記」を解説

2026年4月1日から不動産所有者の住所や氏名の変更登記が義務化され、期限内に申請しないと5万円以下の過料が科される可能性があります。この記事を読めば、義務化の対象者や期限、ご自身で手続きを行うための具体的な手順、必要書類、費用まで全てわかります。相続登記との関係や過去に何度も住所変更したケースなど、あらゆる疑問を解消し、万全の準備ができるようになります。
住所変更登記の義務化は2026年4月1日から
これまで任意とされていた不動産の住所変更登記が、法改正により義務化されることが決定しました。この新しい制度は、2026年(令和8年)4月1日から施行されます。この変更は、不動産を所有するすべての方に関わる重要なルールです。もし手続きを怠ると、過料(罰則)が科される可能性もあります。
この章では、住所変更登記の義務化について、その基本的な内容から背景、対象者、そして最も気になる申請期限と罰則について、分かりやすく解説していきます。
【参考情報】
法務省:住所等変更登記の義務化特設ページ
そもそも住所等変更登記とは
住所等変更登記とは、不動産(土地や建物)の登記簿に記録されている所有者の情報(住所や氏名)を、現在の情報に更新するための手続きです。
不動産の所有者になると、法務局が管理する登記簿にその方の住所と氏名が記録されます。しかし、引越しで住所が変わったり、結婚や離婚で氏名が変わったりしても、自動的に登記簿の情報が更新されるわけではありません。自分で法務局に申請して、初めて登記簿の内容が書き換えられます。
これまでは、この手続きは義務ではありませんでした。しかし、不動産を売却したり、住宅ローンを組むために不動産を担保に入れたりする際には、登記簿上の情報と現在の情報が一致していることが前提となるため、そのタイミングで変更登記を行うのが一般的でした。
なぜ住所変更登記が義務化されるのか
住所変更登記が義務化される最大の理由は、「所有者不明土地問題」の解消です。所有者不明土地とは、登記簿の情報が古いために、現在の所有者が誰なのか、どこに住んでいるのかすぐに分からない土地のことを指します。
この問題が深刻化すると、以下のような弊害が生じます。
- 公共事業(道路建設など)や災害復旧を進めようとしても、土地の所有者と連絡が取れず、用地買収が進まない。
- 周辺の土地の所有者が、隣地との境界を確定させたいと思っても、相手が見つからない。
- 管理が放置された土地が、雑草の繁茂や不法投棄などで周辺環境を悪化させる。
このような問題を解決するため、国は不動産登記法を改正し、所有者の情報を常に最新の状態に保つことを目的として、住所変更登記を義務化することにしたのです。これにより、不動産取引の円滑化や、行政手続きの効率化も期待されています。
住所変更登記義務化の対象者
住所変更登記義務化の対象となるのは、日本国内に不動産(土地・建物)を所有するすべての人(個人・法人)です。具体的には、不動産の登記簿に所有者として名前が記載されている方が対象となります。
- 個人の方:引越しによる住所変更、結婚・離婚・養子縁組などによる氏名の変更があった場合。
- 法人:本店所在地や商号(会社名)を変更した場合。
- 共有名義の不動産:不動産を複数人で共有している場合、共有者一人ひとりが、自身の住所や氏名の変更について登記申請の義務を負います。
つまり、マイホームや相続した土地、投資用マンションなど、何らかの形で不動産を所有している場合は、この新しいルールの対象者となります。
いつまでに申請が必要か 期限と罰則(過料)
住所変更登記の申請には、明確な期限が設けられ、期限を過ぎると罰則が科される可能性があります。
申請の期限は、住所や氏名が変わったタイミングによって異なります。
| 変更が発生したタイミング | 申請期限 |
|---|---|
| 【施行日後】2026年4月1日以降に住所・氏名を変更した場合 | その変更があった日から2年以内 |
| 【施行日前】2026年3月31日以前に住所・氏名を変更し、未登記の場合 | 施行日(2026年4月1日)から2年以内(つまり2028年3月31日まで) |
特に重要なのは、すでに過去に住所変更をしているものの、まだ登記手続きを済ませていないケースです。この場合、法律の施行を待ってから2年間の猶予期間が与えられますので、その間に必ず申請を済ませる必要があります。
もし、正当な理由なくこの申請義務を怠った場合、5万円以下の過料に処される可能性があります。「過料」とは、行政上の秩序を維持するために科される金銭的な制裁であり、刑罰である「罰金」とは異なります。ただし、義務違反に対するペナルティであることに変わりはありません。
なお、「正当な理由」としては、下記が挙げられます。
(1) 検索用情報の申出又は会社法人等番号の登記がされているが、登記官の職権による住所等変更登記の手続がされていない場合
(2) 行政区画の変更等により所有権の登記名義人の住所に変更があった場合
(3) 住所等変更登記の義務を負う者自身に重病等の事情がある場合
(4) 住所等変更登記の義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
(5) 住所等変更登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合
住所等変更登記の義務化のポイント
住所等変更登記の義務化(令和8年4月1日)前の住所や氏名の変更も義務化の対象で、令和8年4月1日から2年以内に登記する必要があります。ですが、「スマート変更登記」を利用することで、法務局が職権で登記してくれるため、義務違反に問われることがなくなります。
義務化の負担を軽減!「スマート変更登記」とは?
2026年4月から始まる住所等変更登記の義務化。引越しや結婚などで住所や氏名が変わるたびに、2年以内に登記申請をしなければならず、「手続きが面倒」「忘れてしまいそう」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。そんな所有者の負担を大幅に軽減するために導入されるのが「スマート変更登記」制度です。
これは、一度簡単な申出をしておけば、その後は法務局が所有者の住所変更などを住基ネットや会社の登記簿で確認し、登記記録を更新してくれる画期的な仕組みです。この制度を利用すれば、ご自身で何度も登記申請をする必要がなくなり、義務違反に問われる心配もなくなります。
【参考情報】
法務省:スマート変更登記のご利用方法
スマート変更登記の仕組みとメリット
スマート変更登記は、法務局が他の公的機関の情報と連携することで実現します。具体的には、個人の場合は「住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)」、法人の場合は「商業・法人登記」の情報を定期的に確認。そこで住所や名称の変更が確認されると、法務局が職権で(=自動的に)不動産の登記情報を最新の状態に書き換えてくれるのです。
この制度を利用するメリットは非常に大きく、主に以下の4点が挙げられます。
| メリット | 具体的な内容 |
|---|---|
| 申請の手間がなくなる | 最初の申出さえ済ませておけば、その後の住所・氏名変更のたびに法務局へ登記申請をする手間が一切不要になります。 |
| 登記漏れと罰則のリスクを回避 | 法務局が自動で変更を検知・登記してくれるため、「うっかり忘れていた」という登記漏れが起こりません。これにより、最大5万円の過料(罰則)を科されるリスクを根本からなくすことができます。 |
| 費用がかからない | スマート変更登記を利用するための申出や、その後の法務局による職権での登記更新に、手数料や登録免許税は一切かかりません。無料で利用できる制度です。 |
| 手続きがかんたん | 利用開始のための申出は、マイナンバーカードがなくてもオンラインで完結できたり、簡単な書類を郵送したりするだけで済みます。専門的な知識がなくても手続きが可能です。 |
利用にかかる費用は?
結論から言うと、スマート変更登記の利用に費用は一切かかりません。無料です。
具体的には、制度を利用するために必要な「検索用情報の申出(個人の場合)」や「会社法人等番号の登記(法人の場合)」といった最初の手続きに、手数料は不要です。また、その後に法務局が職権で行う住所等の変更登記についても、所有者が登録免許税などを支払う必要はありません。
通常、住所変更登記を自分で行う場合でも登録免許税(不動産1筆あたり1,000円)がかかり、司法書士に依頼すればさらに数万円の報酬が必要になります。スマート変更登記は、こうした費用負担をなくし、誰でも気軽に義務化に対応できるように設計された、非常にメリットの大きい制度といえるでしょう。
【個人向け】スマート変更登記の利用方法
個人の方が住所変更登記の義務化に対応し、将来の手間を省くためには「スマート変更登記」の利用が最も効果的です。このサービスを利用するには、無料の「検索用情報の申出」という簡単な手続きを一度行うだけです。ここでは、個人の方向けに、その申出の方法を詳しく解説します。
スマート変更登記を利用するための「検索用情報の申出」とは
「検索用情報の申出」とは、ご自身の氏名、住所、生年月日、メールアドレスなどの情報(検索用情報)をあらかじめ法務局に提供しておく手続きのことです。この申出をしておくことで、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の情報と連携し、住所や氏名に変更があった際に、法務局が職権で変更登記を行ってくれるようになります。
一度この申出を済ませておけば、引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わるたびに自分で登記申請をする必要がなくなり、登記を忘れて過料の対象となるリスクもなくなります。申出は無料で、オンラインでも簡単に行えます。
ケース別:あなたの申出方法をチェック
「検索用情報の申出」の方法は、不動産を所有したタイミングによって異なります。ご自身の状況に合わせて、適切な方法を確認しましょう。
すでに不動産を所有している方(令和7年4月21日より前)
令和7年4月21日より前から不動産を所有している方は、ご自身で「検索用情報の申出」を行う必要があります。この手続きは、令和7年4月21日から受付が開始され、オンラインまたは書面で申し出ることができます。
オンラインでの申出方法
パソコンやスマートフォンから、Webブラウザ上で簡単に手続きができます。専用ソフトのインストールや電子証明書(マイナンバーカードなど)は不要です。
- 利用するサイト:登記・供託オンライン申請システムの「かんたん登記申請」
- 手続き方法:サイトの案内に従い、所有者の情報や不動産の情報を入力して送信します。
- 費用:無料
- メリット:法務局へ行く必要がなく、24時間いつでも手続きが可能です。
書面での申出方法
申出書を作成し、法務局の窓口に持参するか、郵送で提出する方法です。
- 提出先:所有する不動産の所在地を管轄する法務局。複数の不動産を異なる法務局の管轄で所有している場合でも、そのうちのいずれか1つの法務局にまとめて申し出ることができます。
- 提出方法:窓口へ持参、または郵送(書留郵便などが推奨されます)。
申出書に記載する主な情報と、必要な添付書類は以下の通りです。
・申出書記載例(Word PDF)
・申出書様式(Word PDF)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申出情報(申出書に記載) |
|
| 添付書類 |
|
これから不動産を所有する方(令和7年4月21日以降)
令和7年4月21日以降に、売買、相続、贈与などで新たに不動産を取得する方は、所有権の登記を申請する際に、同時に「検索用情報の申出」を行うことができます。
登記申請と同時に申し出る方法
所有権移転登記などの申請書に、従来の記載事項に加えて「検索用情報」を追記するだけで手続きが完了します。別途、申出の手続きを行う必要はありません。
登記申請書に追加で記載が必要となる主な情報は以下の通りです。
| 項目 | 備考 |
|---|---|
| 氏名のフリガナ | 日本国籍でない方は、原則としてローマ字氏名を記載します。 |
| 生年月日 | 本人を特定するための重要な情報となります。 |
| メールアドレス | 職権登記の際の意思確認通知に使われます。ご本人が確実に確認できるアドレスを記載してください。 |
この方法の場合、登記申請のために提出する住民票の写しなどでフリガナや生年月日が確認できるため、基本的に追加の添付書類は不要です。司法書士に登記を依頼する場合でも、これらの情報を伝えれば対応してもらえます。
検索用情報の申出をした後の変更登記までの流れ
「検索用情報の申出」を済ませた後、実際に住所変更があった場合の登記までの流れは、以下の3ステップで自動的に進みます。
- 【ステップ1】法務局による変更情報の確認
法務局が定期的に住基ネットへ照会を行い、申出をされた方の住所や氏名に変更がないかを確認します。 - 【ステップ2】所有者への意思確認(メール通知)
住所等に変更があった方に対して、申出時に登録したメールアドレス宛に「職権で変更登記を行ってよいか」を確認するメールが法務局から送信されます。メールアドレスを登録していない場合は、書面で通知が届くことになります。 - 【ステップ3】職権による変更登記の実行
メールの内容を確認し、所有者が「変更登記に同意する」旨の回答をすると、法務局が職権で不動産の登記簿に記録された住所・氏名を新しいものに書き換えます。これで手続きは完了です。
この仕組みにより、所有者自身は簡単なメール確認だけで、登記義務を果たすことができます。
【法人向け】スマート変更登記の利用方法
法人においても、個人と同様に不動産の住所等変更登記が義務化されました。法人の場合、本店や主たる事務所の移転、商号(名称)の変更がこれに該当します。この義務化による手続きの負担を大幅に軽減するのが、法人向けの「スマート変更登記」です。ここでは、法人がスマート変更登記を利用するための具体的な方法について詳しく解説します。個人とは手続きが異なるため、ぜひご確認ください。
スマート変更登記を利用するための「会社法人等番号の登記」とは
法人がスマート変更登記のメリットを享受するためには、前提として「会社法人等番号の登記」を済ませておく必要があります。これは、法人が所有する不動産の登記記録に、その法人の「会社法人等番号」を記録する手続きのことです。
会社法人等番号とは、法人設立時に法務局から付与される12桁の識別番号です。この番号を不動産登記情報と紐づけることで、法務局が商業・法人登記の変更情報(本店移転や商号変更など)を自動的に検知し、不動産登記簿の所有者情報を職権で(自動的に)更新できるようになります。
つまり、「会社法人等番号の登記」は、商業登記簿と不動産登記簿をつなぐ「橋渡し」の役割を果たし、法人が住所変更のたびに登記申請を行う手間を不要にするための、非常に重要な手続きなのです。
【参考情報】
法務局:所有権の登記名義人による法人識別事項(会社法人等番号等)の申出について
ケース別:あなたの登記・申出方法
「会社法人等番号の登記」を行う方法は、法人が不動産を所有したタイミングによって異なります。具体的には、制度が開始された令和6年4月1日を基準に、手続きが分かれます。ご自身の状況に合わせて、どちらのケースに該当するかを確認してください。
すでに不動産を所有している法人(令和6年4月1日より前)
令和6年4月1日より前から不動産を所有している法人は、「会社法人等番号の申出」という手続きを行うことで、スマート変更登記の対象となります。この申出は義務ではありませんが、今後の変更登記の手間をなくすために、早めに済ませておくことをおすすめします。この申出に費用はかかりません。
申出は、オンラインまたは書面で行うことができます。
| 申出方法 | 概要 |
|---|---|
| オンライン申出 | 法務局の「登記・供託オンライン申請システム」を利用して申出を行います。電子証明書が必要になる場合がありますが、場所を選ばず手続きが可能です。 |
| 書面申出 | 申出書を作成し、不動産の所在地を管轄する法務局へ郵送または持参して提出します。複数の不動産を異なる法務局の管轄で所有している場合でも、そのうちのいずれか一つの法務局にまとめて申し出ることが可能です。 |
申出書には、法人の名称、本店または主たる事務所、会社法人等番号、そして対象となる不動産の不動産番号などを記載します。様式や記載例は法務局のウェブサイトで確認できます。
これから不動産を所有する法人(令和6年4月1日以降)
令和6年4月1日以降に、売買、合併、新築などで新たに不動産を取得し、所有権の登記を申請する法人は、特別な「申出」は不要です。
この場合、所有権の保存登記や移転登記などを申請する際に、申請書に「会社法人等番号」を記載することが義務付けられています。登記申請書に会社法人等番号を記載するだけで、登記が完了すると同時に、その不動産は自動的にスマート変更登記の対象となります。
つまり、これからの不動産取得においては、通常の登記申請プロセスの中で、自動的にスマート変更登記の準備が整う仕組みになっています。これにより、法人が不動産を取得した時点から、将来の本店移転や商号変更に備えることができます。
会社法人等番号の登記がされた後の職権登記までの流れ
一度「会社法人等番号の登記」を済ませてしまえば、その後の手続きは非常にシンプルです。本店移転や商号変更があった際の流れは以下の通りです。
- 法人が通常通り、商業・法人登記の変更手続き(本店移転登記や商号変更登記など)を行います。
- 商業・法人登記の変更が完了すると、その情報が法務局内のシステムを通じて、不動産登記部門に自動で通知されます。
- 通知を受けた不動産登記部門は、その法人が所有する不動産の登記記録(住所や名称)を職権で変更します。
個人の場合と異なり、法人には登記変更の可否を確認する通知は送付されません。商業・法人登記の変更が公的に完了したことをもって、自動的に不動産登記も更新されるため、法人の担当者は特に何もする必要がなく、登記義務を確実に履行できます。
スマート変更登記が利用できないケース
2026年4月から義務化される住所等変更登記の手間を大幅に軽減する「スマート変更登記」。非常に便利な制度ですが、残念ながらすべての方が利用できるわけではありません。スマート変更登記は、法務局が住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)や商業・法人登記の情報を基に、職権で登記情報を更新する仕組みです。そのため、これらの情報源で変更履歴を自動的に追跡できない方は対象外となります。
ここでは、スマート変更登記を利用できない具体的なケースについて詳しく解説します。
海外に居住している個人の方
海外にお住まいの方は、日本の住民基本台帳に登録がないため、法務局が住基ネットを通じて住所の変更情報を把握することができません。そのため、スマート変更登記の対象外となります。
海外在住中に住所(居所)や氏名に変更があった場合は、ご自身で変更登記を申請する義務があります。変更があった日から2年以内に手続きを行わないと、過料の対象となる可能性がありますので注意が必要です。
会社法人等番号のない法人の方
スマート変更登記は、商業・法人登記の情報を基に法人の名称や所在地の変更を反映させます。したがって、商業・法人登記がされていない、又は商業・法人登記がされていても「会社法人等番号(12桁の番号)」を持たない法人は、この制度を利用することができません。
会社法人等番号のない法人の具体例としては、以下のような団体が挙げられます。
- 有限責任事業組合
- 認可地縁団体
これらの法人が所有する不動産について、名称や主たる事務所の所在地に変更があった場合は、個人の方と同様に、変更日から2年以内にご自身で変更登記を申請する必要があります。
スマート変更登記の申出の代行サービス
お忙しい方や色々なご事情があって相談したうえで、スマート変更登記の申出をしたい(代行して欲しい)と考えている方は、司法書士に依頼することをお勧めします。弊所では、5000円(+実費)で全てのお手続きをしていますので、ご検討いただけますと幸いです。
(費用の例)土地1筆と建物1軒の場合、5000円+331円×2=5662円
スマート変更登記に関するよくある質問(Q&A)
住所等変更登記の義務化に伴い導入される「スマート変更登記」。この便利な制度について、多くの方が抱く疑問をQ&A形式でわかりやすく解説します。
Q1. スマート変更登記の申出をすれば、登記義務は果たしたことになりますか?
はい、その通りです。一度「スマート変更登記」の申出を完了すれば、その後、住民票の異動などで住所や氏名が変更された場合、法務局が職権で変更登記を行ってくれるようになります。そのため、ご自身で2年以内に変更登記を申請する必要はなくなり、登記を怠った場合の罰則(過料)の対象にもなりません。
Q2. 申出をすれば、過去の未登記の住所変更も自動で登記されますか?
法務省の「住所等変更登記の義務化に関するQ&A」によると、 過去の未登記についても、スマート変更登記の申出をするだけで大丈夫との記載がありますので、令和8年4月1日以降に、法務局が職権で登記を行うものと思われます。
【参考情報】
法務省:住所等変更登記の義務化に関するQ&A
Q3. 複数の不動産を所有している場合、申出はどうすればよいですか?
複数の不動産を所有している場合でも、申出は一度でまとめて行うことが可能です。
例えば、東京と大阪に不動産を所有している場合、東京の不動産を管轄する法務局か、大阪の不動産を管轄する法務局のどちらか一方に、両方の不動産についての申出をまとめて提出できます。
Q4. 申出に費用はかかりますか?
スマート変更登記の申出(または法人の会社法人等番号の登記)自体に、登録免許税などの費用はかかりません。無料で手続きできます。
Q6. 申出が完了したかどうかは、どうすれば確認できますか?
申出の手続きが法務局で無事に完了すると、申出時に登録したメールアドレス宛に「手続完了」の旨を知らせるメールが届きます。
このメールには、今後の各種手続きに必要となる「認証キー」や、申出を受け付けた法務局、不動産番号などの重要な情報が記載されていますので、大切に保管してください。もしメールが届かない場合は、迷惑メールフォルダなども確認の上、申出先の法務局にお問い合わせください。
【参考情報】
法務省:検索用情報の申出手続が完了した旨の通知メールについて
Q7. 申出の際に登録したメールアドレスを変更したい場合はどうすればいいですか?
申出完了時に法務局から送られてくるメールに記載されている「認証キー」を使用して、メールアドレスの変更手続きを行うことができます。
Q8. スマート変更登記の申出を代行してくれますか?
はい、弊所では5000円(+実費)でお引き受けしております。
(例)土地1筆と建物1軒の場合、5000円+331円×2=5662円
まとめ
2026年4月から、所有者不明土地問題の対策として不動産の住所等変更登記が義務化されます。怠ると過料が科されるため注意が必要です。この負担を軽減するのが、かんたんで便利な「スマート変更登記」制度です。事前に申出をしておけば、住民票や法人登記の変更情報が法務局に通知され、登記官の職権で変更登記が行われます。将来の手間や登記漏れを防ぐためにも、ご自身の状況に合わせて早めに手続きを済ませておきましょう。
ルフレ司法書士事務所では、登記手続きに関する様々な業務を扱っております。司法書士が、迅速丁寧にお客様の状況に合わせた最適なサポートを提供いたします。また、司法書士だけでは解決できない案件については、他士業(弁護士さんや税理士さん等)と連携して業務を行っております。
ルフレ司法書士事務所は、全国対応しております。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。