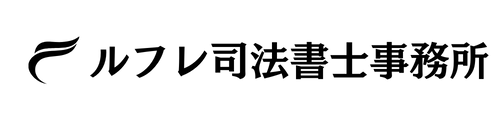あなたの会社の目的変更登記、費用はいくら?知らないと損する登記費用と手続きの注意点
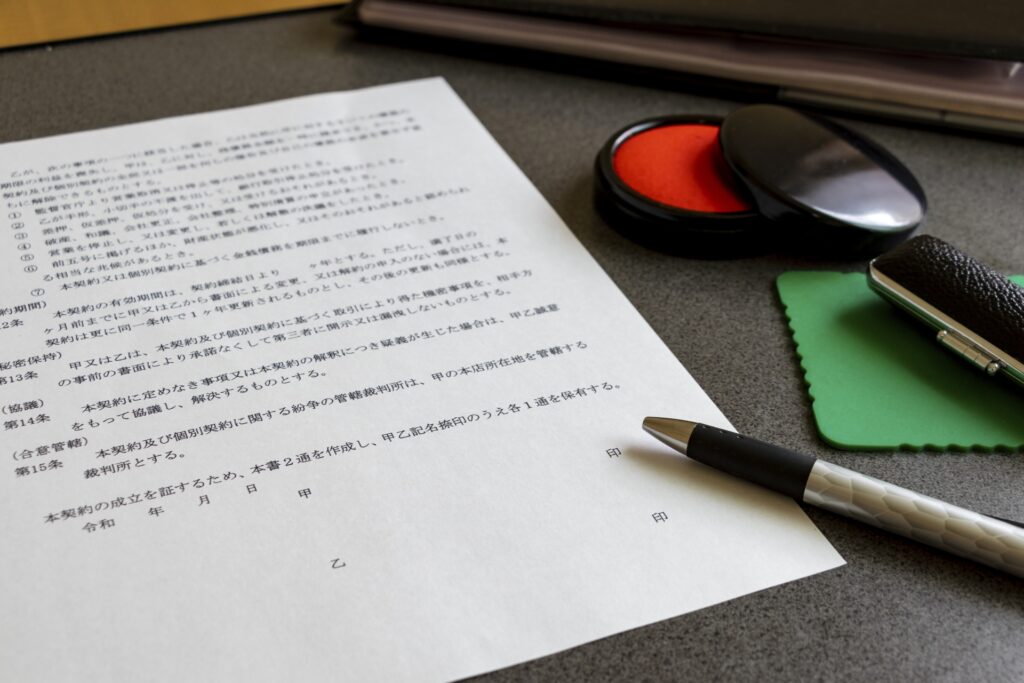
会社の事業内容を変更する際の「目的変更登記」、費用はいくらかかるかご存知ですか?結論から言うと、費用は登録免許税3万円が必須で、司法書士に依頼すると総額5〜7万円程度が相場です。この記事では、目的変更登記にかかる費用の内訳から、自分で手続きして費用を安く抑える方法、具体的な申請手順、注意点までを網羅的に解説します。この記事を読めば、あなたの会社に最適な方法で、無駄なくスムーズに登記を完了させる知識が手に入ります。
会社の目的変更登記とは?なぜ手続きが必要なのか
会社の事業内容は、設立時に作成した「定款」および法務局に登録されている「登記簿謄本(登記事項証明書)」に「目的」として記載されています。この「目的」は、その会社がどのような事業を行うのかを社会に示す、いわば会社のプロフィールのようなものです。会社の目的変更登記とは、この定款と登記簿に記載された事業目的を追加、変更、または削除する手続きのことを指します。
時代の変化や経営戦略の見直しに伴い、新しい事業を始めたり、既存の事業から撤退したりすることは珍しくありません。しかし、会社は定款と登記簿に記載された目的の範囲内でしか事業活動を行うことができません。そのため、実際の事業内容と登記上の目的に齟齬が生じた場合には、速やかに目的変更登記を行う必要があります。この手続きは会社法で定められた義務であり、怠るとペナルティが科される可能性もあるため注意が必要です。
【関連記事】
「商号変更の登記手続きを徹底解説!必要書類から費用、注意点まで」
「会社の役員変更登記のポイント|必要書類・手続き方法・よくあるミスを司法書士が解説」
「【令和7年4月一部改正】本店移転登記の必要書類を徹底解説!司法書士が教える手続き方法」
事業内容の追加や変更時に目的変更登記が必須
会社の目的変更登記が求められる最も一般的なケースは、事業内容に実質的な変更があったときです。具体的には、以下のような状況が考えられます。
- 新規事業への進出:これまでIT関連事業のみを行っていた会社が、新たに飲食店の経営やコンサルティング事業を始める場合。
- 事業の多角化:小売業を営む会社が、オンラインショップの運営や商品の卸売業にも乗り出す場合。
- 事業内容の明確化:創業時には「各種コンサルティング業務」と漠然としていた目的を、より具体的に「経営コンサルティング及びマーケティング支援事業」のように変更する場合。
- 事業の縮小・撤退:複数の事業のうち、不採算部門を整理し、登記簿からもその目的を削除する場合。
目的変更登記を行っておくことは、金融機関から融資を受ける際や、新たな取引先と契約を結ぶ際の信用確保にも繋がります。登記簿は誰でも閲覧できるため、実際の事業内容と登記が一致していることは、会社の透明性と信頼性を示す上で非常に重要です。
許認可の取得に目的変更登記が求められるケース
特定の事業を始めるには、国や都道府県から「許認可」を得る必要があります。この許認可を申請する際、多くの場合、登記簿の「目的」欄に該当する事業内容が明記されていることが前提条件となります。
例えば、中古品を売買する「古物商」の許可を得たい場合、会社の目的に「古物営業法に基づく古物商」といった記載がなければ、警察署は許可申請を受理してくれません。許認可の申請準備を進めてから登記の不備に気づくと、事業開始が大幅に遅れてしまう可能性があります。そのため、許認可が必要な事業を計画している場合は、必ず事前に目的変更登記を済ませておく必要があります。
以下に、許認可の取得に目的変更登記が必要となる代表的な事業の例を挙げます。
| 許認可の種類 | 目的の記載例 | 管轄行政庁(例) |
|---|---|---|
| 建設業許可 | 土木工事業、建築工事業、電気工事業 等 | 国土交通省、都道府県 |
| 宅地建物取引業免許 | 宅地建物取引業、不動産の売買、賃貸及びその仲介 | 国土交通省、都道府県 |
| 古物商許可 | 古物営業法に基づく古物商 | 警察署の生活安全課又は刑事・生活安全課生活安全係 |
| 飲食店営業許可 | 飲食店の経営 | 保健所 |
| 労働者派遣事業許可 | 労働者派遣事業 | 厚生労働省(労働局) |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 産業廃棄物収集運搬業 | 都道府県、政令指定都市 |
上記はあくまで一例です。自社が始めようとしている事業に許認可が必要かどうか、また、その際にどのような目的の記載が求められるかについては、許認可を管轄する行政庁や、専門家へ事前に確認することをおすすめします。
【総額を解説】目的変更の登記にかかる費用の内訳
会社の事業目的を変更する際には、法務局へ目的変更の登記申請が必要です。この手続きにかかる費用は、大きく分けて「必ずかかる実費」と「専門家に依頼する場合の報酬」の2つで構成されます。総額の目安としては、ご自身で手続きを行う場合は3万円、司法書士に依頼する場合は5万円〜7万円程度となります。ここでは、その費用の内訳を詳しく見ていきましょう。
必ずかかる費用 法務局へ納める登録免許税
目的変更登記で必ず発生するのが、法務局に納める「登録免許税」です。これは登記手続きの手数料として国に納める税金であり、金額は会社の資本金の額にかかわらず一律で30,000円です。これは株式会社だけでなく、合同会社や一般社団法人など、すべての法人で同額となっています。
この登録免許税は、登記申請書に30,000円分の収入印紙を貼付して納付するか、オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)の場合は電子納付も可能です。
専門家に依頼する場合の費用 司法書士への報酬相場
登記手続きを司法書士などの専門家に依頼する場合、登録免許税とは別に報酬(手数料)が発生します。司法書士への報酬相場は、一般的に20,000円〜40,000円程度ですが、依頼する業務の範囲によって変動します。
例えば、株主総会議事録などの必要書類の作成から登記申請の代理まで、すべてを依頼するのか、あるいは書類作成は自社で行い申請代理のみを依頼するのかによって金額は変わってきます。また、オンライン申請に対応している司法書士に依頼すると、報酬が比較的安価に設定されているケースもあります。
以下に、ご自身で手続きを行う場合と司法書士に依頼する場合の費用総額の比較をまとめました。
| ご自身で手続きする場合 | 司法書士に依頼する場合 | |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 30,000円 | 30,000円 |
| 司法書士報酬 | 0円 | 20,000円〜40,000円程度 |
| 合計 | 30,000円 | 50,000円〜70,000円程度 |
その他にかかる可能性のある費用
登録免許税や司法書士報酬の他にも、状況に応じて以下のような費用が発生する可能性があります。予算を組む際にはこれらの費用も見込んでおきましょう。
| 項目 | 費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 登記事項証明書(登記簿謄本)の取得費用 | 1通 480円〜600円 | 登記完了後に変更内容を確認するために取得します。オンライン請求・窓口交付が最も安価です。 |
| 代表者の印鑑証明書の取得費用 | 1通 300円〜450円程度 | 司法書士に依頼する場合は、印鑑証明書の提出を求められることが一般的です。 |
| 郵送費・交通費 | 実費 | 法務局へ書類を郵送する場合(レターパックなど)や、直接訪問する場合の交通費です。 |
これらの費用は一つひとつは少額ですが、積み重なると数千円になることもあります。特に、登記完了後に金融機関や取引先へ提出するために登記事項証明書を複数通取得する場合は、その分の費用も計算に入れておきましょう。
目的変更登記の費用を安く抑える3つの方法
会社の目的変更登記にかかる費用は、工夫次第で安く抑えることが可能です。必ず支払う必要がある登録免許税は一律30,000円ですが、それ以外の費用、特に専門家への報酬は変動します。ここでは、登記費用を賢く節約するための3つの具体的な方法を解説します。
自分で登記申請手続きを行う
最も費用を抑えられる方法は、司法書士などの専門家に依頼せず、ご自身で登記申請手続きを行うことです。この方法を選択すれば、司法書士へ支払う報酬(2万円〜4万円程度が相場)を完全に節約できます。
ただし、ご自身で手続きを行う場合は、相応の手間と時間、そして正確な知識が求められます。株主総会の招集から議事録の作成、登記申請書の作成、添付書類の準備まで、すべて自分で行わなければなりません。もし書類に不備があれば、法務局から補正の指示があり、修正して再提出する必要があるため、想定以上に時間がかかってしまうリスクも考慮しておきましょう。
時間に余裕があり、書類作成などの事務作業に抵抗がない方にとっては、コストを最小限に抑えるための有効な選択肢です。
オンライン申請なら費用をさらに抑えられる
ご自身で手続きを行う場合、法務局の窓口へ出向く「書面申請」のほかに、インターネット経由で手続きを行う「オンライン申請(電子申請)」という方法があります。オンライン申請を利用すれば、法務局へ行くための交通費や、書類を郵送するための郵送費を節約できます。
オンライン申請を行うためには、以下の準備が必要です。
- マイナンバーカード(代表者のもの)
- ICカードリーダライタ
- 法務省の「登記・供託オンライン申請システム」の利用者登録
- 申請用総合ソフトのインストール
初期設定に多少の手間はかかりますが、一度環境を整えれば、24時間いつでも自宅やオフィスから申請が可能になり、非常に便利です。書面申請とオンライン申請のコスト比較は以下の通りです。
| 項目 | 書面申請の場合 | オンライン申請の場合 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 30,000円 | 30,000円 |
| 司法書士報酬 | 0円 | 0円 |
| 交通費・郵送費 | 実費(数千円程度) | 0円 |
| 合計費用の目安 | 30,000円 + 実費 | 30,000円 |
このように、オンライン申請は交通費や郵送費といった細かな経費を削減できるため、最も安く目的変更登記を済ませる方法と言えます。
他の登記手続きとまとめて依頼する
もし目的変更登記のタイミングで、他に「役員変更」や「本店移転」といった登記手続きの予定がある場合は、まとめて司法書士に依頼することで費用を抑えられる可能性があります。
多くの司法書士事務所では、複数の登記を同時に依頼すると、個別に依頼するよりも報酬が割安になるケースが一般的です。これは、司法書士側も一度に手続きを進めることで、手間や時間を効率化できるためです。
登記申請の手間も一度で済み、トータルの費用も安くなるため、一石二鳥の方法です。近いうちに役員の任期が満了する、本店の移転を検討しているといった場合は、目的変更と同時に手続きできないか司法書士に相談してみましょう。
自分でやる方向け 目的変更登記の手続きと流れを5ステップで解説
会社の目的変更登記は、司法書士に依頼せず自分で行うことで、報酬分の費用を数万円単位で節約できます。手続き自体は複雑に思えるかもしれませんが、一つひとつのステップを丁寧に進めれば決して難しいものではありません。ここでは、専門家に頼らずご自身で目的変更登記を完了させるための具体的な手順を5つのステップに分けて詳しく解説します。
ステップ1 新しい事業目的を決定する
まず最初に行うべきは、会社の定款に追加・変更する新しい事業目的を具体的に決定することです。この事業目的は、登記申請後に会社の「登記事項証明書(登記簿謄本)」に記載され、会社の事業内容を公に示す重要な情報となります。特に融資や許認可を受ける場合は、目的の記載内容に注意が必要となります。目的を決定する際は、以下の3つのポイントを必ず確認してください。
- 適法性:公序良俗に反する事業や、法律で禁止されている事業を目的とすることはできません。
- 明確性:誰が読んでも事業内容を具体的に理解できる、分かりやすい言葉で表現する必要があります。抽象的すぎる表現は登記官に認められない可能性があります。(例:「商業」→「各種商品の企画、製造、販売及び輸出入」)
- 営利性:株式会社は営利を目的とする法人であるため、「ボランティア活動」や「寄付行為」といった非営利活動のみを目的とすることはできません。
また、将来的に展開する可能性のある事業も、この機会に目的として追加しておくことをお勧めします。事業を開始するたびに目的変更登記を行うと、その都度3万円の登録免許税と手間がかかるため、少し幅を持たせた目的を記載しておくと効率的です。
ステップ2 株主総会で定款変更の特別決議を行う
事業目的は会社の定款に記載されているため、目的を変更・追加するには定款そのものを変更する必要があります。定款の変更は、会社の組織や運営に関する最も重要な決定事項の一つであり、株主総会での「特別決議」を経なければなりません。
特別決議は、普通決議よりも可決要件が厳しく設定されています。具体的には、以下の要件を満たす必要があります。
- 議決権を行使できる株主の過半数(定款で3分の1以上と定めることも可)が出席すること
- 出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成を得ること
株主総会を開催し、定款変更について特別決議で承認されたら、その内容を証明する「株主総会議事録」を作成します。この議事録は、後の登記申請で必要不可欠な書類となります。
ステップ3 登記申請に必要な書類を作成する
株主総会での決議が終わったら、法務局へ提出する登記申請書類一式を作成します。不備があると手続きが遅れる原因となるため、慎重に準備を進めましょう。主な必要書類は以下の通りです。
目的変更登記申請書
登記申請のメインとなる書類です。書面申請をする場合は、法務局のウェブサイトでテンプレート(ひな形はこちら)が提供されているため、ダウンロードして使用するのが便利です。オンライン申請の場合は、申請用総合ソフトの操作手順(手順はこちら)に従い、申請書情報を作成します。記載すべき主な項目は以下の通りです。
| 項目 | 記載内容・注意点 |
|---|---|
| 商号 | 会社の正式名称を記載します。 |
| 本店 | 会社の本店所在地を記載します。 |
| 登記の事由 | 「目的の変更」と記載します。 |
| 登記すべき事項 | 変更年月日と、変更後の事業目的すべてを記載します。「令和○年○月○日変更」「目的」と記載し、新しい目的を箇条書きで入力します。この部分は、別紙(Wordなどで作成)やCD-R等で提出することも可能です。 |
| 登録免許税 | 「金30,000円」と記載します。収入印紙を貼付するための台紙(A4の白紙で可)に3万円分の収入印紙を貼り付け、申請書とホチキスで留めます。※オンライン申請の場合は電子納付が可能です。 |
| 添付書類 | 提出する書類の名称(株主総会議事録、株主リストなど)を記載します。 |
| 申請人・代表取締役 | 会社の本店所在地、商号、代表取締役の住所・氏名を記載し、法務局に登録している会社実印(代表者印)を押印します。 |
株主総会議事録
ステップ2で解説した、定款変更の特別決議が適法に行われたことを証明する書類です。法律で定められた記載事項が漏れなく記載されている必要があります。
- 株主総会の開催日時及び場所
- 議事の経過の要領及びその結果
- 出席した取締役、監査役等の氏名
- 議長の氏名
- 議事録を作成した取締役の氏名
- 総株主の数、発行済株式の総数、議決権を行使できる株主の数及びその議決権の数
- 出席株主数及びその議決権の数
- 定款変更の議案、賛成した株主の議決権の数、可決された旨
作成後、議長及び出席取締役が記名押印することが一般的ですが、登記手続きで提出する場合は、必ずしも押印が必要なわけではありません。※定款で押印についての定めがある場合は、そちらの規程に従います。
株主リスト
株主総会の決議の正当性を担保するために添付が義務付けられている書類です。株主総会で議決権を行使した株主について、以下のいずれかに該当する株主の情報を記載します。
- 議決権数上位10名の株主
- 議決権割合が2/3に達するまでの株主(上位株主から順に加算)
上記のうち、いずれか株主数が少ない方を選択して作成します。株主の氏名・住所、株式数、議決権数、議決権数割合を記載し、会社実印(代表者印)で押印しますが、登記手続きで提出する場合は、必ずしも押印が必要なわけではありません。
ステップ4 管轄の法務局へ登記申請を行う
必要書類一式が完成したら、会社の「本店所在地」を管轄する法務局へ登記申請を行います。管轄外の法務局に提出しても受理されないため、事前に法務局のウェブサイトで管轄を確認しておきましょう。申請期限は、目的変更の効力発生日から2週間以内と定められているため、注意が必要です。
申請方法は以下の3つです。
- 窓口申請:法務局の窓口へ直接書類を持参する方法です。書類の不備をその場で指摘してもらえる可能性がありますが、開庁時間内(平日8:30~17:15)に行く必要があります。
- 郵送申請:書類一式を封筒に入れ、管轄法務局宛に郵送する方法です。法務局へ出向く手間が省けます。
- オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム):専用ソフトのインストールや電子署名が必要ですが、自宅やオフィスから24時間申請が可能です。登録免許税の納付もインターネットバンキング等で行えます。
申請後、書類に不備がなければ1週間から2週間程度(1か月程度かかる法務局もあります)で登記が完了します。もし不備があった場合は、法務局から電話で連絡があり、「補正」を求められます。指示に従って書類を修正し、再提出してください。
ステップ5 登記完了後の手続き
不動産登記と違い、法務局の手続きが完了しても登記を完了したことを証明する登記完了証や登記識別情報のような権利証は発行されません。
変更後の登記内容を確認したい場合は、別途、登記簿謄本(登記事項証明書)を窓口又は登記・供託オンライン申請システムで請求するか、登記情報提供サービスで確認します。費用は登記簿謄本の場合、オンライン請求で窓口受け取る場合が一番安く490円(郵送で送ってもらう場合は520円、書面申請の場合は600円)、登記情報サービスで閲覧する場合、331円です。
登記完了までの期間は、法務局の混雑状況にもよりますが、通常1週間から1か月程度です。
手続きの注意点
金融機関から融資を受ける場合や、許認可を受ける場合は、事前に目的の記載内容について確認することが重要です。登記完了後に修正する場合、費用も時間もかかるため、当初の予定通りに進める事が難しくなります。
まとめ
会社の目的変更登記は、事業内容の追加や許認可取得に必須の手続きです。費用は、法務局に納める登録免許税3万円に加え、司法書士に依頼する場合は報酬が発生します。費用を抑えたいなら、自分でオンライン申請を行ったり、複数の司法書士から見積もりを取ったりする方法が有効です。変更後2週間以内の申請期限を守り、適切な手続きを行うことが重要です。本記事を参考に、自社の状況に合った最適な方法を選択し、事業の成長に繋げてください。
ルフレ司法書士事務所では、会社の登記に関する様々な業務を扱っております。司法書士が、迅速丁寧にお客様の状況に合わせた最適なサポートを提供いたします。
会社の手続きでお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。